|
鶴岡八幡宮
|
八幡宮の総本宮
八幡さまとは応神天皇の御神霊で、天皇がなくなられたのち、欽明天皇の32年(571)に初めて九州大分の宇佐の地に御示顕になったとのこと。宇佐は神代に比売大神が天降られて早くから開け、神武天皇の皇軍を迎えた聖地で、そこに建立された宇佐神宮が八幡宮の総本宮で、全国に四万社あまりの分社がある。
 宇佐神宮は、皇室では伊勢神宮に次ぐ御先祖の神社として崇敬され、特に勅使の和気清麿が国体を正す神教を授けたことで有名である。本殿は奈良朝の神亀年間の創立で三つの御殿があり、国宝に指定された皮葺丹塗の八幡造りで、20年毎に塗り替えられる。祭神は、一之御殿 八幡大神(応神天皇)、二之御殿 比売大神(多岐津姫命、市杵島命、多紀理姫命)、三之御殿 息長帯姫命(神功皇后)。例祭日は3月18日で、この日には、鶴岡八幡宮をはじめ各地の八幡宮で宇佐神宮遙拝式が行われる。
宇佐神宮は、皇室では伊勢神宮に次ぐ御先祖の神社として崇敬され、特に勅使の和気清麿が国体を正す神教を授けたことで有名である。本殿は奈良朝の神亀年間の創立で三つの御殿があり、国宝に指定された皮葺丹塗の八幡造りで、20年毎に塗り替えられる。祭神は、一之御殿 八幡大神(応神天皇)、二之御殿 比売大神(多岐津姫命、市杵島命、多紀理姫命)、三之御殿 息長帯姫命(神功皇后)。例祭日は3月18日で、この日には、鶴岡八幡宮をはじめ各地の八幡宮で宇佐神宮遙拝式が行われる。
鶴岡八幡宮創建の経緯
清和天皇のときの貞観元年(859)に、僧行教により平安京の鎮護として宇佐神宮から分霊して石清水八幡宮が創建された。そして康平6年(1063)に源頼朝の先祖である鎮守府将軍陸奥守源頼義が、朝廷より奥州安部氏追討の宣旨を受け、「前九年の役」で勝利をおさめたことの礼として鎌倉の由比郷より小林郷北山の地を聖地と定め、仮宮殿を造り、伊豆渇山権現の僧を迎え石清水八幡宮を勧請して祀った若宮(元八幡)が始まりといわれる。この社は元八幡(下社)として今も残っている。
治承4年(1180)に鎌倉を本拠に定めた源頼朝が、神社を政権の中心地とした現在地に移したが、神社と幕府の建物は建久2年(1191)3月4日に小町からの出火で焼失した。頼朝が同年11月21日に再建した神社に石清水宮を勧請し、幕府の公的祭祀を行う場所と定めたのが、鶴岡八幡宮である。
 |
(上の写真は平成15年11月21日に撮影)
本殿と祭神
現在の上宮一帯の社殿群は、文政11年(1828)に第十一代将軍徳川家斉公により造営された代表的な江戸建築だが、鎌倉時代の造りを見事に蘇らせており、平成8年7月に国重要文化財に指定されている。本殿には、祭神として八幡大神(応神天皇)と息長帯姫命(神功皇后、景行天皇の后)を祀っている。石段の右側にある若宮は、寛永3年(1626)に第二代将軍徳川秀忠公が建立した最古の社で、若宮(下宮)には仁徳天皇、同妃盤媛履仲天皇、同妃仲媛の四柱を祀る。なお、当時は神仏混淆で「鶴岡八幡宮寺」と呼ばれ、社域には中央に本尊として阿弥陀如来、左右に不動明王と釈迦如来を祀る真言宗と、阿弥陀如来を本尊として祀る臨済宗の寺棟が併設されていたが、明治6年の神仏分離令により仏教関係は田谷の洞窟に移された。
なお、保管されていた仏教の経典600巻が江の島で焼き捨てられようとしたが、参詣に来ていた浅草芸者が通りかかり、その経典を譲り受け浅草寺に奉納したという。その経典は国宝に指定されている。真言宗と浄土宗の寺には必ず槙の木が植えられているが、鶴岡八幡宮にも槙があり、神仏混淆の時代があった歴史の跡を残している。
大鳥居
海浜の若宮大路に立つ一の鳥居は大鳥居と呼ばれ、高さ8.5m、柱の太さ92cmで花崗岩を使っている。源頼朝の時代に創建された鳥居は木造で度々造り替えられたが、寛文8年(1668)に石造となった。その鳥居は関東大震災で倒壊したため、昭和初期に一部新材を補って復旧したのが現在の鳥居で、国指定重要文化財である。東側柱の旧材部分に「寛文八年戊申八月十五日 御再興 鶴岡八幡宮石雙華表」と刻まれてある。
段葛(だんかずら)と狛犬
 寿永元年(1181)に、源頼朝が妻 北条政子の安産と、武家幕府の礎を固めることを祈願し、由比ケ浜海岸と八幡宮を結ぶ1800mに及ぶ段葛の参道を、京都の朱雀大路を模して造らせた。明治22年の横須賀線開通により第一の鳥居から第二鳥居までの段葛は取り除かれたが、二の鳥居から、鶴岡八幡宮前の第三の鳥居までの457mの段葛は今も残っている。二の鳥居の参道の幅は5mであるが、三の鳥居の幅は2.3mで、八幡宮に向かって参道が長く見えるようになっており、反対に八幡宮からは参道の幅が平行に見えるように遠近法を使ってつくられている。東側(右側)は幕府の本拠地で地盤が高く、西側は葛石が高く盛ってあり、東西南北から敵を守るように造られてある。
寿永元年(1181)に、源頼朝が妻 北条政子の安産と、武家幕府の礎を固めることを祈願し、由比ケ浜海岸と八幡宮を結ぶ1800mに及ぶ段葛の参道を、京都の朱雀大路を模して造らせた。明治22年の横須賀線開通により第一の鳥居から第二鳥居までの段葛は取り除かれたが、二の鳥居から、鶴岡八幡宮前の第三の鳥居までの457mの段葛は今も残っている。二の鳥居の参道の幅は5mであるが、三の鳥居の幅は2.3mで、八幡宮に向かって参道が長く見えるようになっており、反対に八幡宮からは参道の幅が平行に見えるように遠近法を使ってつくられている。東側(右側)は幕府の本拠地で地盤が高く、西側は葛石が高く盛ってあり、東西南北から敵を守るように造られてある。
参道両側には、明治までは松、大正年間には梅が植えられていたというが、現在は桜並木で、春には夜桜が楽しめる。

![]()
![]()
第二鳥居の入口には寛文8年(1668)建立の狛犬が参拝者を迎えてくれる。狛犬は、一千柱の神々の館を守る役を負っているといわれ、右の口を開いた「ア」は、陽を意味し人間の産声の姿で、左の口を閉じた「ウン」は陰で人間の死を意味し、両狛犬の間が人生を現しているといわれ、神域の鬼門を守っており、「阿」「うん」の呼吸という語源ともなっている。
源氏池と平家池
三の鳥居をくぐると中央に太鼓橋がある。男が転ばずに渡れば出世する、女が渡れば安産できる‥‥との願いを込めて造成されたといわれる。現在は老朽化したため、通行禁止となっている。
両隣にある通行用の橋を渡り参道を進むと、右側には治承4年(1180)に、北条政子が源頼朝の必勝を祈願し、産(=栄える)の願いを込めて三つの島を浮かばせ、源氏の旗色である白の花が咲く蓮を植えさせた源氏池がある。一番大きい島には鎌倉七福神の一つに指定されている旗上弁財天が祀られ、源頼朝公の旗上げにちなみ、源氏の二引きの旗に願をかける参拝者で賑わう。御社殿は八幡宮御創建800年(昭和55年)に、文政年間の古図をもとに復元したといわれる。
参道の左側には、四つ(死=滅びる)の島を築き、紅蓮を植えさせ平家の滅亡を祈願したと伝わる平家池がある。両池を挟む参道の両側には、文久2年(1862)に大阪、江戸の砂糖問屋が奉納した大きな石灯篭が建っている。
 |
 |
(平家池) (源氏池)
かくれ銀杏本殿に続く石段左手に、樹齢千年以上で{かくれ銀杏」といわれる銀杏の大樹がある。
承久元年(1219)正月27日、八幡宮では右大臣となった28歳の第三代将軍源実朝の就任拝賀式典が雪の降る中行われた。夜も更けて京都の公卿達が立ち並ぶ前を松明を握り先導する前駆の後に、参拝を終えた実朝が石段を下りてきた。その時、頭巾を被って大銀杏の木に隠れていた法師が、「親のカタキはかく討つゾ」と一太刀を浴びせ、首を打ち落とした。その法師は阿闍梨公暁(あじゃりくぎょう)で、数千の武士達は鳥居の外に控えていたため惨劇はたやすく演じられたと……。
しかし、銀杏はせいぜい樹齢七百年以上のもので、公暁が実朝に切りかかった場所が大銀杏の側との記述は古い資料には記載されていない。上記の「かくれ銀杏」の記述は江戸時代になってからの逸話のようである。
舞殿と静御前
本殿に至る石段の手前に唐破風の入母屋造りの下拝殿がある。源義経の側室となった静御前は名うての白拍子で、雪深い吉野山で義経と行き別れとなり、捕らえられて鎌倉に送られた。文治2年(1186)4月8日、北条政子の所望により、舞殿で舞の奉納をすることになった。
よしの山 みねのしら雪ふみわけて いりにし人 の あとそこひしき
しづやしづ しづのをだまきくり返し 昔を今に なすよしもがな
と歌いながら舞ったという。「静御前」の舞は、源頼朝が期待した舞ではなく、義経を恋慕い別れを悲しむ想いが込められていたため、頼朝は激怒したという。その時義経の子を身篭もっていた静は、鎌倉から出ることを許されず同年7月に男児を産んだが、頼朝の命により、由比ガ浜で命を奪われてしまう。同年9月に帰洛を許された静御前の消息は定かではないという。毎年4月の鎌倉祭りの日曜日に、この舞台で静の舞が再現されるが、その悲しい逸話の舞台は、現在の建物の前にあった若宮社殿であったという。
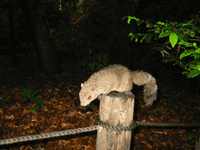 鶴岡文庫
鶴岡文庫
本殿裏の左手奥に、「鶴岡文庫」と呼ぶ図書館がある。神社所蔵の国宝や古文書が保管されてある。入館料は無料で、原則として、年末年始及び月曜日以外の午前9時〜午後5時まで開館している。なお、鎌倉や日本の文化に関する一年単位の教養講座が開設されている。
(お宮に住みついているリス)
鎌倉国宝館
舞殿の左方に昭和3年に開館した国宝館がある。鶴岡八幡宮に伝わる資料だけではなく、鎌倉に伝わる国宝や重要文化財に指定された仏像なども展示されてある。
国宝指定:太刀 銘 正恒(備中青江鍛冶系の正恒による鎌倉時代の作)、朱塗弓・黒漆矢・沃懸地杏葉螺鈿平胡グイ、沃懸地杏葉螺鈿太刀、古神宝類の御神服五領(御祭神の一柱、神功皇后の御神服)、籬菊螺鈿蒔絵硯箱(源頼朝公が後白河法皇より下賜されたものを奉納) 「開館 9:00〜16:00 休館:月、祝日の翌日」
歴史探訪の会へ戻る