|
光明寺(こうみょうじ) 材木座6−17-19 |
浄土宗大本山 天照山蓮華院
寛元元年(1243)に、鎌倉幕府四代執権北条経時が開基。開山は浄土宗第三祖、然阿良忠(ねんありょうちゅう)。良忠上人は、正治元年(1199)7月27日、石見国三隅庄(現在の島根県)に生まれ16歳で出家し、修行の後、二祖の聖光房弁長上人の許に修学し、関東に念仏の教えを広め多数の寺院を建立、門弟を育成し百巻に及ぶ著書を残した。89歳で入寂後に第九十二代伏見天皇(1288〜98)から記主(きしゅ)禅師の謚号を贈られた名僧である。
当寺は鎌倉中期の創建で、第百三代後土御門天皇より「関東総本山」の称号を受け勅願寺となった名刹で、建長寺、円覚寺、遊行寺とともに鎌倉四代寺院といわれている。
第九世観誉祐崇上人の明応4年(1495)に、御土御門天皇の勅使によって10月12日より15日に至る間、十夜法要が行われてから今日までその法要は続いている。お十夜の間は、無数の灯明に照らされた大伽藍の中や開山堂に夜を徹して御詠歌や念仏を唱える声が響き、沿道には植木市や露店が並ぶ。徳川家康公は、当寺を関東十八檀林(幕府が定めた学問所)の筆頭におき、宗学の発展道場として、この寺を芝の増上寺とともに重要視したといわれている。別名「お十夜さんの寺」と呼ばれ庶民から親しまれている寺である。
総門をぐぐり、境内を進むと二層の山門があり、奥の中央にある大殿の屋根には勅願寺の象徴である菊の御紋が輝いている。境内の右手に、動物供養塔、宋の善道上人自ら彫った獅子像が四面を巡っている鐘楼堂、繁栄稲荷社、延命地蔵尊があり、左手には開山堂、書院、記主庭園、大聖閣がある。
総門
最初の門が創建されたのは、明応4年(1495)といわれ、門の掲額「勅願所」は観誉祐崇上人の直筆と伝わる。現在の建物は寛永年間(1624〜28)の再建で、釘など一切使われていない。藁座が上下に彫られた門の開閉が出来る六本の柱から造られており、文化的価値が感じられる。(鎌倉市指定文化財)
山門
最初の山門は鶴岡八幡宮寺から移築されたが、現存の山門は弘化4年(1847)の再建で、間口約16m、奥行約7m、高さ約20m、鎌倉の寺院では最大の格式を備え、五間三戸(正面からみて柱より5つに間仕切りされていて、中央の3つの間にはそれぞれ両開きの大板戸がありそれが入り口になっているもの)の二階二重門と呼ばれている。
一階は日本風、二階は中国風に造られ、それを支える中央の江戸時代の原木を使った二本の丸柱は、大人二人の腕を廻しても余る程の太さで軒裏までの通し柱である。
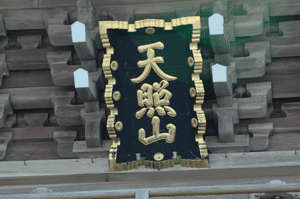 二階中央に「天照山」と書かれた畳一帖程の大きな扁額があり、その字は第百二代後花園天皇のご宸筆で、永享8年(1436)に下賜されたが、天皇が額字をしたためるにあたり、空、無相、無願の三つを念じ、仏に帰す‥‥ことを心に入れて筆を走らせたと伝わっている。
二階中央に「天照山」と書かれた畳一帖程の大きな扁額があり、その字は第百二代後花園天皇のご宸筆で、永享8年(1436)に下賜されたが、天皇が額字をしたためるにあたり、空、無相、無願の三つを念じ、仏に帰す‥‥ことを心に入れて筆を走らせたと伝わっている。
二階には釈迦如来を中心に、左に普賢菩薩、右に文殊菩薩の釈迦三尊像、その周りには仏を守る持国天(東)、廣目天(西)、増長天(南)、多聞天(北)の四天王像が、その左右に十六羅漢像が祀られている。
なお、総門は、お寺の入り口を示す門のことで、主な門は山門(三門)である。山門を入ることは、お寺の聖域(浄界)に入ることを自覚して拝観すべきである。
 大殿
大殿
檜と杉の大木からなる十四間四面の雄大な建物で、庭園、庫裏、書院、開山堂が渡り廊下で繋がっている。
元禄11年(1698)第五十二世白玄上人の時代に再建された。現存する木造の古い建築では、鎌倉一の大堂である。
本堂内中央に、本尊として西方極楽浄土に居住し、無限の光と寿命を持っている阿弥陀如来、脇侍として観音菩薩と勢至菩薩が祀られ、専修念仏根本道場の威厳を醸し出している。
右檀には、二祖、聖光上人より拝受したと伝わる等身大の善導大師立像と、もと江ノ島弁財天であったと伝わる弁財天像が安置されている。左檀上には、如意輪観音像と開祖、法然上人像が祀られている。
開山堂

開山堂には、良忠上人、歴代法主の御影が祀ってある。最初の開山堂は、大正12年(1923)の関東大震災で倒壊したため、翌13年に古材などで再建されたが、老朽化したため平成14年(2002)に真新しいお堂が再建された。
石造地蔵菩薩
境内の右手に建っている有形文化財で、扇ヶ谷にある浄光明寺の綱引き地蔵とこの地蔵が三角点で結ばれており、海の安全と大漁が祈願されている。
三尊五祖の庭
 三尊とは阿弥陀如来と脇侍の観音・勢至両菩薩を指し、五祖とは、釈尊(インド)、善導大師(中国)、法然上人(宗祖)、鎮西上人(第二祖)、良忠上人(第三祖)の浄土宗五大祖師を指している。この庭は京都の竜安寺にならい、この世から浄土を拝み衆生を導かれる願いを込めて造られた枯山水の庭園である。仏に見立てた敷石が流れる雲に乗って浄土に向かう形をしているといわれ、敷き詰められた砂石が掃き清められてあり静かな庭園を眺めていると心が清められる。
三尊とは阿弥陀如来と脇侍の観音・勢至両菩薩を指し、五祖とは、釈尊(インド)、善導大師(中国)、法然上人(宗祖)、鎮西上人(第二祖)、良忠上人(第三祖)の浄土宗五大祖師を指している。この庭は京都の竜安寺にならい、この世から浄土を拝み衆生を導かれる願いを込めて造られた枯山水の庭園である。仏に見立てた敷石が流れる雲に乗って浄土に向かう形をしているといわれ、敷き詰められた砂石が掃き清められてあり静かな庭園を眺めていると心が清められる。
(注)善導大師は、唐代の浄土教の高僧で、法然上人に心の師として大きな影響を与えた。
記主庭園
 本堂と開山堂を結ぶ回廊の奥に、名古屋城天守閣や二條城を築造したり、二條城二の丸庭園などを作庭した小堀遠州が造ったといわれる瓢箪形をした池泉式庭園があり、開山の記主禅師の名から記主庭園と呼ばれている。
本堂と開山堂を結ぶ回廊の奥に、名古屋城天守閣や二條城を築造したり、二條城二の丸庭園などを作庭した小堀遠州が造ったといわれる瓢箪形をした池泉式庭園があり、開山の記主禅師の名から記主庭園と呼ばれている。
昭和26年、千葉市検見川遺跡で縄文時代のものと思われる丸木舟が複数発掘されたが、その遺跡の地下6mから大賀一郎東京大学農学部教授が、古代ハスの種3粒を発見した。この種は、2000年以上地下で眠っていたとのことで、その種を撒いたところ、その年の5月に1粒が発芽、翌年7月18日には淡紅色の花を咲かせた。
この池には「二千年ハス(大賀ハス)」と「千年古代ハスと雑種の掛け合わせたハス」がこの庭園の池に群生しており、7月下旬から8月中旬まで、古代のロマンが漂う桃色の美しい花を楽しめる。なお、抹茶を頂きながらの観蓮会(有料)も行われている。
 |
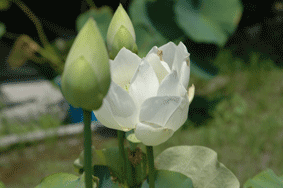 |
鐘楼堂
総欅瓦葺きの鐘楼堂は、弘化4年(1847)の建造。堂に架かる現在の梵鐘は、昭和36年の法然上人七百五十年遠忌として鋳造せられたもので、朝・夕に打ち鳴らす荘厳な鐘音を鎌倉の市街に響かせている。
繁栄稲荷社
この寺を開山した良忠上人は、佐助ヶ谷に住んでいた時に狐児を助けたことがある。その後上人の夢枕に親狐が現れ、狐児を助けてくれたお礼にと、薬種袋を置いて姿を消した。上人がその種を撒き成長した葉茎を煎じて病人に与えたら、たちどころに病が癒えたという。感激した上人はこれぞ佐助稲荷の神助と当山に正一位稲荷大明神を勧請し、社を建て信仰したという。爾来この社はこの寺の鎮守となっている。
天照神明社・秋葉社と廟所・墓地
本堂の背後の山を総称して「天照山」という。本堂の右側から背後の山を上ると、山中に天照・春日・八幡の三神を祀る神明社がある。そこから山道を上ると神奈川県景勝50選の展望台があり、山頂には火災盗難を防ぐ寺域の鎮守、秋葉大権現が祀られてある。三十三世深譽伝察上人が身を天狗に現じて当山を守護したとの寺伝がある。天照山山頂の奥に、良忠上人の廟、その隣りに北条経時(法名 蓮華寺殿安楽大禅定門)の宝篋印塔がある。この寺を開基した北条経時は、鎌倉四代将軍藤原頼経と五代将軍藤原頼嗣を補佐し、寛元4年(1246)に執権を時頼に譲り出家して安樂と号したが、34歳の若さでこの世を去ったという。北条経時一族の墓、そして歴代住職の墓も立ち並んでいる。
光明寺の境内から少し離れているが、寺の東側に在る材木座幼稚園の隣接地に鎌倉市指定史跡の内藤家の墓所がある。
内藤家墓所
日向国延岡城主と磐城湯長谷領主を兼ね、徳川直参の本田政高の家老職だった藩主・内藤家一族の墓所。最初は江戸深川霊願寺にあったが、内藤忠興公(磐城平7万石で、延宝2年(1674)没)の代に先祖一族の墓などを光明寺の寺域に移したといわれる。
 |
 |
巨大な墓碑58基(宝篋印塔40基、笠塔婆12基、仏像形4基、五輪塔形宇1基、角塔婆形1基)、灯籠118基、手水鉢17基、地蔵尊等九基が墓地に集中して林立しており、江戸時代初期以来の石仏など代々の大名の墓が全部一ヶ所にまとまっているのは全国的にも大変珍しく、また壮観で、昭和37年9月7日に鎌倉市指定の史跡となっている。年代により墓石の形も変わっており、頭部が欠けている数体の地蔵尊以外は、損傷していない。どのようにして此処に運んだのか、また、関東大震災でも倒壊しなかった石工技術からも貴重な文化財といわれている。
九品寺へ