 |
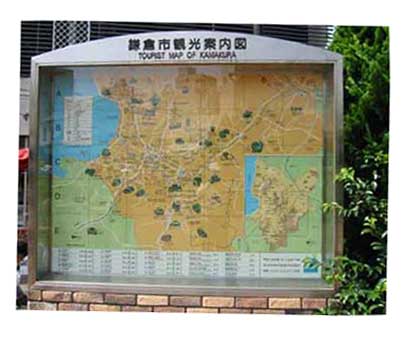 |
治承4年(1180)8月に伊豆で旗揚げした源頼朝が、石橋山の戦で敗れたものの、関東一円の平氏の武士団の支持を得て、同年10月7日に源氏の祖先のゆかりの地鎌倉に入り本拠地としました。そして、東国の支配権を確立した頼朝は、弟の範頼・義経を派遣して壇ノ浦で平家を滅ぼし、更に北辺の雄、藤原氏を倒して天下統一を果たしました。建久2年(1192)7月12日に、頼朝は征夷大将軍(鎌倉殿)になり、京の都に対して最初から防御を主眼においた町造りをして東国武士による鎌倉幕府を築きました。鎌倉は南が海、他の三方は山に囲まれた要害の地で、交通路として三方の山を切り崩し、尾根を削り、切岸を造った上に兵士などが駐在できる平場の切り通しを7ヶ所設けました。
「鎌倉」の名前の謂われは、様々な伝説や地形的な説など書物に書かれてある主なものでも8つあるといわれていますが、どれが本当かははっきりしません。「鎌」は、かまどのことで、「倉」は谷で、つまり、「かまど谷」という説があります。鎌倉の地形が東・西・北の三方が山で南が海になっていることから、地形が「かまど」のような形をしており、小さな谷もこのような形が多いので、一番解りやすい説であると思います。
平安時代は、連帯性の政治が行われていましたが、鎌倉時代は独裁制になり、土肥、和田、梶原、大庭、畠山、千葉、三浦、安達、比企、北条の10氏が家来として源頼朝に仕えました。正治元年(1199)1月に頼朝は落馬により突然死去、二代将軍の頼家は、元久元年(1204)に北条時政に殺害され、三代将軍の実朝も頼家の子・公暁によって鶴岡八幡宮で暗殺され源氏の正統は、鎌倉幕府の発足から27年、わずか三代で途切れました。
頼朝亡き後は北条氏を中心に関東武士同士の勝ち抜き合戦が始まり、北条氏は、最初に梶原、畠山、比企を滅ぼしたあと和田も滅ぼして、宝治元年(1240)には三浦も滅ぼし実権を一族の手中に収め、第三代将軍源実朝以後、北条時政が北条執権の政権を確立しました。第五代執権北条時頼の時代になって鎌倉幕府は安定し、7ヶ所の切り通しの入り口に建長寺、円覚寺、極楽寺、浄明寺などの大伽藍の寺や長谷の大仏を建立しました。
北条執権は第十六代守時まで続きましたが、元弘3年(1333)に北条氏に滅ぼされた関東武士の子孫が、京都での反乱に乗じて、源氏の子孫である新田義貞を中心に立ち上がり、極楽寺坂、化粧坂、巨福呂坂の三つの切通しから鎌倉攻めを行いました。極楽寺坂切り通しから攻めた義貞軍は北条軍に反撃されましたが、稲村ヶ崎から海沿いに再進撃を行い切通しの要害を突破し、挙兵から14日目に官邸のあった東勝寺に北条軍を追い込みました。そして、北条一門870余名は祇園山で腹を切って幕府は滅亡しました。
百四十余年間の幕府と武家社会の幾多の遺跡は、その中で生きた人間のロマンと情熱の歩みの跡を残しています。鎌倉時代に比叡山で平安仏教の天台宗(最澄)・真言宗(空海)を学んだ高僧により、臨済宗(栄西)、浄土宗(法然)、浄土真宗(親鸞)、曹洞宗(道元)、時宗(一遍)、日蓮宗(日蓮)の六宗派がこの鎌倉の地で生まれました。鎌倉には臨済宗41寺、日蓮宗32寺、真言宗16寺、浄土宗11寺、時宗7寺、天台宗2寺、曹洞宗2寺、浄土真宗1寺の合計112寺が現存しています。
歴史の重みを醸し出している古都鎌倉には、鎌倉時代の歴史の証しである鶴岡八幡宮をはじめ多くの神社、古刹、武将とそれを取り巻く古戦場、聖地などがあり、四季折々の花や樹木が散策者を楽しませてくれます。八百年前の武士や聖者を囲む夢とロマン、そして野望と情熱の世界に触れる「鎌倉歴史探訪」をお勧めします。
鎌倉駅西口改札口前の広場には、旧鎌倉駅にあった「時計塔」と、第二次世界大戦時に古都鎌倉を戦火から守る努力をされたラングドン・ウォーナー氏の「顕彰碑」があります。

|
 第二次世界大戦時に、米国の美術学者で日本古美術および文化を研鑚されたDr.Langdon Warner ラングドン・ウォーナー(1881〜1955)が、当時の大統領ルーズベルトに”Calture Takes Precedence Over War.” (文化は戦争に優先する)との名句を送り、京都・奈良・鎌倉の三古都をはじめ日本全土にわたる芸術的、歴史的建造物には、決して戦禍の及ばぬよう強く訴えられました。 第二次世界大戦時に、米国の美術学者で日本古美術および文化を研鑚されたDr.Langdon Warner ラングドン・ウォーナー(1881〜1955)が、当時の大統領ルーズベルトに”Calture Takes Precedence Over War.” (文化は戦争に優先する)との名句を送り、京都・奈良・鎌倉の三古都をはじめ日本全土にわたる芸術的、歴史的建造物には、決して戦禍の及ばぬよう強く訴えられました。鎌倉市民憲章に、「博士は、夙に日本古美術および文化を研鑚し、造詣すこぶる深かった。太平洋戦争の勃発に際し氏は、日本の三古都をはじめ全土にわたる芸術的歴史的建造物には、決して戦禍の及ばぬよう強く訴えた。そして日本の多くの文化財は爆撃を免れた。博士の主張の成果というべきであろう。われら鎌倉を愛する有志相計り、古都保存法制定20周年を機として、ウォーナー博士が歴史と文化の保護に示した強靭な意志を永く伝え、学ぶため記念碑を建てる。 |
|
文部省唱歌 「鎌 倉」
|
|
作詞:芳賀矢一 作曲:不詳
|
|
1. 七里ヶ浜(しちりがはま)の磯づたい
|
|
稲村ヶ崎(いなむらがさき)名将の
|
|
剣(つるぎ)投ぜし古戦場
|
|
2. 極楽寺坂(ごくらくじざか)越え行けば
|
| 長谷観音(はせかんのん)の堂近く |
|
露坐(ろざ)の大仏おわします
|
| 3. 由比(ゆい)の浜辺を右に見て |
| 雪の下道(したみち)過ぎ行けば |
| 八幡宮(はちまんぐう)の御社(おんやしろ) |
| 4. 上(のぼ)るや石のきざはしの |
| 左に高き大銀杏(おおいちょう) |
| 問わばや遠き世々(よよ)の跡 |
| 5. 若宮堂(わかみやどう)の舞の袖 |
| しずのおだまきくりかえし |
| 返せし人をしのびつつ |
| 6. 鎌倉宮(かまくらぐう)にもうでては |
| 尽きせぬ親王(みこ)のみうらみに |
| 悲憤の涙わきぬべし |
| 7. 歴史は長き七百年(しちひゃくねん) |
| 興亡すべて夢に似て |
| 英雄墓は苔むしぬ |
| 8. 建長・円覚(えんがく)古寺(ふるでら)の |
| 山門高き松風に |
| 昔の音やこもるらん |