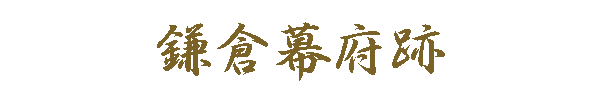 |
1.大蔵幕府跡(1180〜1225)ー雪の下3−11
治承4年(1180)10月に、富士川の合戦で平家に勝った源頼朝は鎌倉に入り、 鶴岡八幡宮の東側に居館を建て、その屋敷に入り侍所を設置した。
元歴元年(1184)には公文所(のちの政所)、問注所を置き、さらに翌年3月には壇ノ浦で平家を滅亡へと追い込んだ。そして、奥州藤原氏を平定、建久3年(1192)7月12日に源頼朝は征夷大将軍となり、鎌倉幕府が成立した。
八幡宮東側に隣接する横浜国立大のさらに東側、現在の清泉女学院の周辺東西2町半 (約270m)、南北2町(約210m)の広大な敷地が鎌倉に開かれた最初の幕府で、四面門を設けて門外の地を東御門(みかど)、西御門、南御門等と称した。この地が大倉であったことから「大蔵幕府」と呼ばれている。東御門跡(西御門2−8)、西御門跡(雪の下3−5)にもその石碑が建っているので、周囲をまわるとそのおおよその規模が類推できる。
源頼朝は、相模川の架橋の完成祝いに出かけた時に落馬。それが原因で翌年の正治元年(1199)に53歳で死去した。頼朝の墓は、大蔵幕府跡の北側の小高い山の上にある。山上から眺めると下が平地になっているのが分かるが、その辺り一帯が頼朝屋敷であった。
建保元年(1213)5月、和田義盛が北条義時と争った時戦火で屋敷は全焼。実朝は、直ちに再建を行い障子の絵を京都に依頼するなどして、従来のものとは異なった屋敷が完成したといわれている。幕府が宇都宮辻子に移る までの46年間、この地が鎌倉幕府の中心だった。
嘉禄元年(1225)に北条政子が亡くなり(69歳)、同年10月、藤原頼経の新幕府となってこの屋敷は取り壊されたが、跡地は江戸時代までは記念として幕府跡として他に使用されることはなっかった。清泉小学校の側に「大蔵幕府跡」の石碑が建っている。
「今ヲ距ル七百三十七年ノ昔治承四年源頼朝邸ヲ此ノ地ニ營ミ後覇權ヲ握ルニ及ビテ政ヲ此ノ邸中ニ聴ク所謂大蔵幕府是ナリ爾来頼家 實朝ヲ経テ嘉禄元年政子薨ジ幕府ノ宇津宮辻ニ遷レルマデ此ノ地ガ覇府ノ中心タリシコト實ニ四十六年間ナリ」
大正六年三月建之 鎌倉町青年會
頼朝の死後、二代将軍となった長男の頼家は、建仁2年(1202)7月22日に従二位征夷大将軍に就任した。政子の父である北条時政と、頼家の妻、若狭局の父である比企能員((ひきよしかず)は、共に将軍家の外戚として勢力を争うようになった。頼家は、従来の習慣を無視し独裁的判断を行うようになったが、政治の実権は頼朝の妻で「尼将軍」といわれる政子の親族北条氏へと移っていった。
建仁3年(1203)に頼家が病に倒れると後継問題が持ち上がり、若狭局が生んだ頼家の子一幡(いちまん)を擁する比企氏と、頼家の弟千幡(せんまん・後の三代将軍実朝)を推す北条氏が衝突した。一幡と実朝に相続させる合議がなされると、反発した頼家は比企氏と組み北条氏討伐を計ったが、北条氏は対立する比企能員を謀殺し、現在妙本寺が建つ場所にあった比企氏の館を襲撃して一族を滅亡させた。頼家は将軍職を剥奪され伊豆の修禅寺に幽閉され、元久元年(1204)7月に北条氏からの刺客により暗殺された。
建暦3年(1213)には、北条氏は和田一族を滅亡させるなど、頼朝旗上げ以来の有力御家人を次々に排斥していった。政子のお気に入りであった実朝が三代将軍となり、承久元年(1219)正月27日、鶴岡八幡宮で右大臣となった28歳の第三代将軍源実朝の就任拝賀式典が雪の降る中行われた。夜も更けて京都の公卿達が立ち並ぶ前を松明を握り先導する前駆の後に、参拝を終えた実朝が石段を下りてきた。その時、頭巾を被って大銀杏の木に隠れていた法師が、「親のカタキはかく討つゾ」と一太刀を浴びせ、首を打ち落とした。その法師は頼家の子(実朝の甥)の阿闍梨公暁(あじゃりくぎょう)で、源氏の血脈は、鎌倉幕府開府後30年も続かずに途絶えてしまったのである。
2.宇津宮辻子幕府跡(1225〜1236)ー小町2−15
三代将軍実朝の死後、政子は北条義時を初代執権とした。元仁元年(1224)6月13日に義時が没すると、北条泰時を二代執権とした。嘉禄元年(1225)に大江広元と叔母政子が他界すると、泰時は心機一転を期して、幕府を大蔵から若宮大路と小町大路に囲まれた宇津宮辻子に館を移転した。寛喜元年(1229)には、頼朝の姉の子で、二歳の藤原頼経を京より征夷大将軍として迎え、建長4年(1254)までの27年間ここに幕府を置いた。幕府といって居館の座敷で協議などを行ない、特別な建物は建てなかった。
現在、この場所には幕府邸の守護神だった稲荷大明神の祠が建っている。小路を左に進んだ大仏次郎邸の横に、幕府跡の碑が建っている。
藤原頼経は、頼家の娘、良子と結婚させられ、11年間将軍職に就かせたが、その後京に追い返され悲運の末路をたどった。頼経は、在任中に十二所に五大堂王院を建立したが、その古刹が鎌倉での足跡として残されている。
宇津宮氏の氏神、稲荷神社前に、「宇津宮辻幕府跡」と刻まれた辻子の「子」の字が抜けた石碑が建っている。(注)辻子とは、二つの大路を結ぶ小道のこと。
鎌倉幕府を支えた重鎮大江広元は嘉禄元年(1225)6月に死去、あとを追うように尼将軍とよばれた北条政子は、1ヶ月後の10月に69年の波乱に富んだ人生を閉じた。
政子が42歳の時に頼朝が死去して以来、政子と大政治家大江広元とのロマンスが、鎌倉幕府と北条氏の強化安定につながったと歴史は語っている。
3.若宮大路幕府跡(1236〜1333)ー雪の下1ー11
俗に親王屋敷とも呼ばれ、元弘3年(1333)に、第十六代守時が北条一門870余名とともに祇園山で腹を切って幕府が滅亡するまで、四代将軍藤原頼経から、宗尊親王、惟康親王、久明親王、九代将軍守邦親王まで将軍職は受け継がれた。
鶴岡八幡宮前の旧横大路に面していたという説と、位置は、宇都宮辻子幕府跡と同じだが、出入り口が若宮大路に面していたという説に分かれている。何れにしてもこの近くに権力者だった北条泰時の屋敷があった。幕府が幕を下ろした場所に碑が建っている。
鎌倉散策コース一覧へ戻る