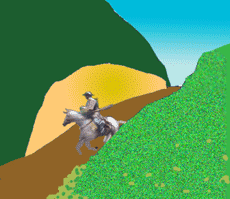鎌倉七切り通し
鎌倉は南西が相模湾で、他の三方は山に囲まれた天然要害の地です。鎌倉幕府は鎌倉への往来が便利になる交通路として三方の山を切り崩し、切り通しを設け尾根を削り切岸を造り、その上に兵士が駐在できる平場を造って外部侵入の防御を固めました。その切り通しは、以下の7ヶ所です。
|
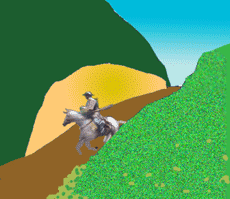 |
亀ヶ谷坂(かめがやつざか)切り通し(扇ヶ谷)
扇ヶ谷から山ノ内を経て武蔵国に通じる道で、北条時頼が4323人の人夫を集め、3ヶ月を要して完成した‥‥との史実が残っている。坂を登って行く亀が急坂のため途中でひっくり返ったのでこの名前が付けられたともいわれている。坂の頂上に「峠の茶屋」と書いた標示があり、誰が置いたのか小さな椅子が四個ある。厳しく切り立つ苔の生えた崖の両側は深い樹木に覆われ、静寂な雰囲気は今も古道の面影を残している。
化粧坂(けわいざか)切り通し(扇ヶ谷)
気生、形勢、仮粧とも表記され、吾妻鏡には「気和飛坂」と書かれている。元弘3年(1333)の新田義貞による鎌倉攻めの主戦場となった所で、急勾配で岩がごつごつしているが、武蔵国へ通じている。名前の由来は源平の戦で、平家の武将の首を化粧して首実験をしたから、この坂の麓に娼家があったから、険しい坂からなど諸説がある。当時は盛り場であったが、今は人通りも少ない。
名越(なごえ)切り通し(大町)
鎌倉と逗子・三浦を結ぶ道で北条氏に滅ぼされた三浦一族の悲話が残る道。
巨福呂坂(こぶくろざか)切り通し(雪の下)
北条泰時が、仁治元年(1240)に防衛、物資の輸送のため険難だった主要街道を修造したと伝わる。当時は、北鎌倉から建長寺を通り、鶴岡八幡宮に抜ける道路の西側の山道を超えていく坂道であった。時宗の開祖一遍上人が、布教のため鎌倉入りしようとした時に北条 時宗に拒否され、この坂で一夜を明かしたといわれ、京都、武蔵国からの主要道路であった。現在はこの道の途中に当時の面影を残す十二基の石碑が建ち並んでいるが道路は行き止まりで、 付近は私有地となっている。現在は、当時の切り通しの代わりとして、明治19年に開通した道路に巨福坂洞門(トンネル)が架かっている。
大仏坂(だぶつざか)切り通し(長谷)
古くは深沢切り通しと呼ばれたが、藤沢から武蔵国に通じる道で、現在の長谷遂道の上にある。
極楽寺坂(ごくらくじざか)切り通し(極楽寺)
極楽寺を開山した忍性が開いたといわれ、腰越・片瀬を経て東海道・京の都への西の守り口となった。鎌倉幕府倒幕のため攻めてきた新田義貞が、強固な木戸で閉ざされたこの切り通しに阻まれ、稲村ヶ崎からの海路に廻った史実からも、この切り通しは軍事的に重要であった。
朝比奈(あさひな)切り通し(十二所)
源頼朝の家臣和田義盛の子、朝比奈三郎義秀が一晩で切り開いたとの伝説からこの名が残り、昔ながらの旧状を留めている。吾妻鏡には、仁治元年(1240)11月に新道造営を決議し、翌2年4月に着工、三代執権北条泰時自らが監督して土石を運んだ‥‥とある。六浦と鎌倉を結ぶ六浦道にあり、俗に塩の道と呼ばれ、当時は安房・上総・下総から物資が集められ、六浦の塩・米を鎌倉に運ぶ経済路であった。また、房総への退路として軍事上の要地でもあった。東京湾に浮かぶ野島と富士山を結ぶ線上に岩山が切られていることは見事であるが、現在は新道の開通により通る人も少なくなった。
鎌倉十井

鎌倉の井戸は、昔から良質の水に恵まれなかったため、水質の良い水が湧き出るもの及び伝説が伝わる10ヶ所の井戸が、鎌倉十井(じゅっせい)と呼ばれ、歴史に名を残しています。
(左の写真は甘露の井)
棟立の井(むなたてのい)
覚園寺の裏にある。山からの清水が家屋の棟立の形をした石下から湧き出ていることから名付けられたといわれ、弘法大師が掘った井戸との説もある。
鉄の井(くろがねのい)
鶴岡八幡宮そばの鎌倉街道と横大路の交差点の南側にある。この井戸から鉄製の観音像が発掘されたことから「鉄の井」といわれるようになった。なお、この仏像は扇ガ谷にあった新清水寺のものだったとも伝えられており、現在は、東京人形町の大観音寺の本尊となっている。この井戸水は、第二次大戦の時にポンプが付けられ、防火用水として使用されていたという。
六角の井(ろっかくのい)
和賀江島の近くにある。八角形の井戸であるが、二角は逗子の分で、六角が鎌倉の分ということでこの名がつけられたという。保元の乱で敗れ、伊豆大島に流された鎮西八郎為朝が、光明寺の裏山の天照山目掛けて射った矢がこの井戸に落ち、村人が矢を抜いたが4,5寸の鏃が井戸に残ったとの伝えがあり、「矢ノ根井」ともいわれている。
底脱の井(そこぬけのい)
扇ヶ谷の海蔵寺山門の向かい右側にある。平泰盛の娘、無著如大(幼名は千代能)がここに水を汲みにきた時、水桶の底がすっぽり抜け、その時悟りを開いたとの伝説があり、この時に、「千代能が いただく桶の底ぬけて 水たまらねば 月もやどらず」と詠んだのでこの名がつけられたという。
甘露の井(かんろのい)
浄智寺の境内の石段近くにある井戸で、源頼朝がこの井戸のために貫高を寄付したとの伝説もある。甘くて綺麗な水であったことからこの名が付けられたいわれている。
泉の井(いずみのい)
扇ヶ谷の浄光明寺門前にあり、現在も綺麗な泉をたたえている。名前の謂れは特にないようであるが、この辺りはこの井戸の名前から泉ヶ谷と呼ばれている。
瓶の井(つるべのい)
明月院の境内の宗猷堂近くにある。岩を掘り抜いた時に出た井戸で、現在も庭の散水に使用されているという。
扇の井(おいぎのい)
飯盛山の麓の民家の裏庭にあるため、自由に見学できないが、開いた扇の形のような井戸で、源義経の愛妾静御前が、舞扇をここに納めたともいわれている。亀ヶ谷坂を下ってきた旅人の貴重な飲み水であったという。
星の井(ほしのい)
星月の井、星月夜の井とも呼ばれており、極楽坂下の虚空蔵堂前にある。この辺りは昼でも暗く、井戸を覗くと星が見えたといわれ、江戸期の紀行文や歌にこの井戸の名が出ている。昭和初期までは旅人にこの井戸水が売られていたそうだ。
銚子の井(ちょうしのい)
名越の長勝寺の境内の岩を切り抜いて掘られた井戸で、寺の道を隔てた向かい側にある。井戸側は石で、全体の形が長柄の銚子に似ているためこの名が付いたというが、「石ノ井」ともいわれている。石蓋は六枚の花弁に似た形をしている。
鎌倉五名水
銭洗水
源氏山の麓の岩山をくりぬいたトンネルをくぐると奉納鳥居が林立する銭洗弁財天宇賀福神社の境内にでる。本殿左手奥の洞窟内に奥宮があり、ここに湧き出る霊水でお金を洗うと何倍にも増える‥‥と信仰されている。ザルと柄杓も用意されているのでお札を洗う人もいるようだが、「十分ご縁がありますように」との願を込めて10円玉と5円玉を洗い、5円玉のみを財布の中にしまっておくとご利益があるといわれている。
梶原太刀洗水
十二所から朝比奈切り通しに入る三郎の滝近くにある。梶原平三景時が、寿永2年(1183)に源頼朝の蜜命により、上総介千葉広常を不意討ちした時に、この湧き水で血刀を洗ったといわれている。
日蓮乞水
旧名越切り通しへの道あり、日蓮が旅の途中で、喉が渇き水を欲しくなって杖を突き刺すとそこから水が湧き出たといわれる井戸水。
甘露水
浄智寺山門前にある石橋の下の湧き水で、鎌倉十井の一つの甘露の井の水。
|