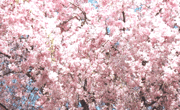前夜からの続き
|
第201夜から第205夜まで
|
|
第201夜 - 墓碑銘
|
|
アダム・スミスの『道徳感情論』のなかで、ある名も知らない人の墓碑銘が引かれています。 (アダム・スミス 『道徳感情論』(上) より) |
|
第202夜 - グローカリゼーション
|
| これはミスタイプではありません。グローバリズムとローカリズムを結びつけた造語(glocalization)です。「グローバリゼーション」が正確な定義もなく世の中での経済の常識語となってしまっています。しかし、経済がそして文化がグローバル化すればするほど、その一方でローカルな経済や文化が際立つようになります。グローバルな商品が画一的となると同時にローカルな多様性が生み出されるのです。文化や生活様式は決して世界的な画一性をもたらしません。何もかも画一的な商品や文化になってしまえば何と味気のない世界になるでしょう。画一化の反面でローカルなものが際立ってくるわけです。したがってグローバリズムとローカリズムは対立するのではなく、双方が複合化されて実現されるものなのです。この意味である学者は「ローカルなもののグローバル化とグローバルなもののローカル化」と言って「グローカリゼーション」と名付けました(ロバートソン)。逆説的な面白い見方ですね。例えばマクドナルドのような商品が世界的に広がれば、夫々の国や地域で自分たちのアイデンティティ(例えば牛丼や回転寿司)を確認するためにこれに対抗する文化を掘り起こし大切に守るということが要請されるようになる、というわけです。だから今日の食文化の多様性が見られるのかもしれません。 |
|
第203夜 - グローバリズムの逆説
|
| グローバリズムは「グローブ(地球的)」から派生した言葉です。では国際的(インターナショナル)という言葉とどう違うのでしょうか。両者を区別するものは、国家の存在です。インターナショナルという言葉を用いるとき、それは必ず主権国家を前提にしています。それに対してグローバリズムは超国家的な主体が前提になっていると言えましょう。しかし本当に国家を超えたグローバリズムは存在するでしょうか。最も積極的なグローバル化の動きはアメリカによる「民主主義」と「市場経済」のグローバル化です。やはりアメリカという国家のもとに進められているのです。超国家的な主体の相互依存による世界の普遍的一体化というカントの「世界市民」のような理想ではありません。グローバリズムとは、「個別主義」が普遍化したものというパラドキシカルな見方をすればお叱りを受けるかもしれません。しかし、佐伯啓思氏は、公共的市民精神をもったナショナリズムを「シヴィック・ナショナリズム」と呼んでグローバリズムの無軌道な暴走を牽制する必要があると力説するのです。
(参考: 佐伯啓思 『倫理としてのナショナリズム』より) |
| 第204夜 - 銀行家は眠りこけている? |
| ワルラスの一般均衡論を高く評価したシュンペーターでしたが、そのワルラスには銀行家は登場していません。居たとしても眠りこけていると森嶋通夫氏はいいます。ところがそのシュンペーターは銀行家の役割を重要視します。彼の唱える「新結合=イノベーションinnovation」には資金が必要だからです。経済が定常状態にあるとき(これを経済学では静態といいます)は、貯蓄や資本蓄積は一切行われないから、そのかわりにシュンペーターは銀行家を登場させるのです。ただし、彼の銀行家のイメージは資本家としてのイメージでなく、この新結合をファイナンスする或いはサポートする役割(支配するというのではなくて)を担う、信用創造にあります。貯蓄の増加を通じて資本蓄積が進行するというアダム・スミス以来の正統派見解への批判でもありました。そうするとワルラスとシュンペーターとは随分異なった見解だと思えるのですが、それでもシュンペーターがワルラスを高く評価したということはどこに理由があるのでしょう。おそらく「ハテナ」はこう考えます。シュンペーターの『経済発展の理論』の前半は、静態を扱っています(”静態に利潤なし”とは有名な言葉です)。そして信用創造を持ち出し発展の理論を構築していきます。この前半の導入部分で彼はワルラスに負うところが大きかったのではないかと見ていますが・・・或いはワルラスにも動態の考えがあった? |
|
第205夜 - 重商主義は重工主義
|
| フリードリッヒ・リストの言ったように、「重商主義とは実は重工主義」なのです。重商主義はアダム・スミス以来経済学者には概して評判が良くありません。批判の焦点は、重商主義が(国内生産力の増大という真の目標を忘れて)貿易黒字の拡大という二次的な目標にこだわりすぎたというところに置かれています。しかし改めて重商主義の主張を検討してみますと、単なる貿易黒字、単に特権商人を利するためだけの政策とみなすのは単純すぎるようです。重商主義は「重工主義」、あるいは「開発主義」の一つの初期的な表現であるともいえましょう。そのとおり18世紀が深まると、資本主義と国民国家が充分に「開発」され、重商主義がいよいよ本格的に「重工主義」化せざるを得なくなります。じつはそのことをはっきりと指摘したのが、まさにアダム・スミスの『国富論』だったのだ、という見方も成り立つように思われます。 |