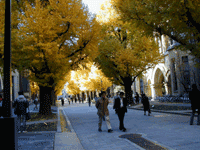前夜からの続き
|
第331夜から第335夜まで
|
|
第331夜 - プライマリー・バランス
|
| わが国の財政赤字の累増を何とか抑える方法なり考え方はないものかということでプライマリー・バランスという用語が登場しました。今日のわが国の財政状態は、GDPが約500兆円で今後年2パーセントの経済成長が見込めるとすれば、年間約10兆円のGDPが増えることになります。租税負担率(社会保障負担を除く)が現在の25〜30パーセントだとしますと、年間に増える税収は2兆5000億円から3兆円となります。仮に1年間に3兆円の税収増加で645兆円の財政赤字を埋めるとして、いったい何年かかるのでしょうか?645兆円÷3兆円=215年間も要することになってしまうのです。 そこで生まれた概念が、プライマリー・バランスという考え方です。プライマリー・バランスとは、「歳入から国債収入を除き、歳出から国債の元本と利払い費である国債費を引いた分を、差し引きしたもの」であります。つまり、「租税と税外収入という基礎的な歳入で、借金返済以外の基礎的な歳出をどれだけ賄えるか」ということであります。言い換えれば(多少意地悪く言えば)国債問題を棚上げにして、国債関連を除いた部分で歳入と歳出を均衡させる、そこで余った分が出てくればその分を国債費や元本に充当する、とにかく国債以外での基礎的収支を均衡させようではないか、という考えで生まれた概念です。このプライマリー・バランスは、現在16兆円弱の赤字ですから、まずこれを均衡させることが第一でこれなら出来なくはない、ここから収支を均衡させようという発想が出てきたわけです。これ以上赤字を出してわが国の財政を破綻させたくないとして生まれた概念ではありますが、その一方で国債とその償還を先送りした(何と200年以上もかかる!)議論ですね。プライマリー・バランスを保てば国債の増加は防げましょうが、既存の国債の処理は次世代へ、またその先の世代へと先送らざるをえず、これは”永久国債”だと「ハテナ」は思ってしまいます。 (参考:川北隆雄『経済論戦ーいま何が問われているのかー』岩波新書より。カッコ内は同書p.146-147より引用しました) |
|
第332夜 - Unite or Die
|
|
アメリカ独立革命に貢献した人々のうちの一人、ベンジャミン・フランクリンは、植民地連合計画(オールバニー連合案)を促進するために版画を彫ったのでしたが、そのなかに、「連合か死か」(Unite or Die またはJoin or Die)というスローガンがあり、これを共和制支持派新聞であるニューヨーク・ジャーナル紙の題字に載せました。以前の題字は英王室のシンボルが描かれていたのでしたが、1774年にそのシンボルに変えてこのスローガンを持ってきたため、この言葉は有名になりました。 (参照:ロン・チャーナウ『アレグサンダー・ハミルトン伝』アメリカを近代国家につくり上げた天才政治家ーより) |
| 第333夜 -戦うハミルトン |
|
以下は、アメリカ独立戦争でのアレグザンダー・ハミルトンのエピソードです。アメリカの独立を阻止しようとする英国軍は、1777年7月の初めには、国王ジョージ3世が「勝ったぞ!アメリカ人をたたきつぶせ」と喜んだように優勢でありました。なにしろイギリスのハウ将軍率いる艦隊は267隻18000人の陣容でした。これに果敢に挑んだのが若き日のハミルトンでした。英国軍の掃射に会ってハミルトンたちは渦巻く激流に飛び込み泳いで安全な場所にたどりつきました。その時アメリカの司令部は、ハミルトンが川で死んだという知らせを受けていました。そこへずぶ濡れの死体本人が、ふらふらとドアから入ってきたのです。司令部には歓喜の涙があふれ、ついで大爆笑がわき起こった、ということです。後の財務長官としてアメリカを近代国家に仕上げたハミルトンの若き日の行動の一齣です。『ハミルトン伝』の著者、ロン・チャーナウは、ハミルトンの「真に優れた男は、ひいき目に見ていてはわからず、逆境によって見出されるということに気づいた」という言説を引用しています。 (『アレグザンダー・ハミルトン伝』 p.192-193, p.283) |
| 第334夜 - 銀行とは? |
|
G・エドワード・グリフィンの『マネーを生みだす怪物』(吉田利子訳)には、アメリカの連邦準備制度を容赦なく批判しているやや通俗的な物語であります。原題は、THE CREATURE FROM JEKYLL ISLAND (ジキル島でうまれたもの)ですが、その謂れは本書を見れば一目瞭然です。しかし今夜は、本書の「はじめに」で、のっけから”銀行って何だろう”という問題をQ&Aの形で始めています。かなり長い質問と答えが連綿と続きます(英国のユーモア雑誌「パンチ」からの引用です)。文意を損なわない程度に要約して以下に掲げてみましょう。それでも長すぎる? Q: (銀行の広告に)資産5億ドルとも書いてあるけれど、これも儲けたお金? こうしたパロディがずっと続きます。でも長くなるから途中をカットして続きを次夜にいたしましょう。 |
|
第335夜 - 続・銀行とは?
|
| 【前夜からの続き】
Q: ・・・銀行に貸しておけば、それは銀行の「負債」だと言っただろう?金を引き出して「負 債」を減らしてやれば、銀行は喜ぶんじゃないのか? このパロディ、どう思われますか? (参照:エドワード・グリフィン『マネーを生みだす怪物』−連邦準備制度という壮大な詐欺システム p.13-17) |