前夜からの続き
|
第466夜から第470夜まで
|
|
第466夜 - 騎士道の起源
|
| 騎士道とはいったいどんな精神でしょうか。今日ではジェントルマンにふさわしい道と考えられがちでありますが、騎士道の起源は決してそのような正しい礼儀から発したものではなく、人間本性の根源にもとづいて発生してきたといえます。例えば、モスナーという学者は、以下のように騎士道の生まれを説いています。
・・・ロマンティックな騎士道(Romantick Chivalry)、あるいは騎士の諸国遍歴(Knight-Errantry)という怪物(Monster)が、人間本性の原理の必然的な作用によって世界に現れることになった。注目すべき点は、それがムーア人とアラビア人から伝えられたことである。彼らは、征服した諸地域からローマ人の礼節について多少学んでおり、一般には北の人間よりも鋭敏で発明の才があると目されている南の人であったが、彼らは偉業の達成というこうした特質を思いついた最初の人たちだった。それがいったん立ち現れると、これらの国民と同じ状態にあるヨーロッパ中をほんのわずかな火花で焚き付け、燃えさかる火のように覆いつくしたのである。(壽里竜氏訳) このように、ローマの暴政がいかに大きくても、圧制下の人々の技芸の洗練さをことごとく追放してしまうわけではありません。それどころか逆にローマ帝国を襲った野蛮人たちは、ローマ人を模倣し彼らとの生活様式の一致を見出そうとするのです。やがて自らの神さえも放棄しローマの神々と交換しさえもします。さらには美徳は理性を超えて中庸の度を遙かに超えた華々しい奇想や空想をあおり、駆け巡るようにさえなります。この妄想が他を引き離し自らの長所と思いこむようになり、さらに徳や洗練さまでに浄化していくとき、騎士道が生まれる、とモスナーは言うのです。 (参考:モスナー(Ernest Campbell Mossner) David Hume's "An Historical Essays on Chivalry and Modern Honour") |
| 第467夜 - オセロウ |
| ヒュームが前夜のように騎士道の起源の一部に挙げているムーア人とはいったいどのような人種でしょうか。「ハテナ」にとって大変興味深く思われるのは、このムーア人がシェイクスピア(1564-1616)の悲劇『オセロ』の主人公として登場していることです。比較的小編にあたる『オセロ』(第1幕から第5幕まで、岩波文庫で198頁)のなかで、訳注、解説を除きムーア人の名は実に50箇所に亘って登場しています。いったいシェイクスピアは、何故この悲劇の主人公にムーア人を配したのでしょうか?シェイクスピアは、『ヴェニスの商人』と同じく舞台設定の場所をブリテンに置かず『オセロウ』を再びヴェニスとサイプラス島に置いています。にもかかわらずブリテンの人々は、1604年に公演されたこの『オセロウ』に涙したことでした。ハムレットが蒼白の美青年なら、オセロウは筋骨逞しい黒人で、旗手を務めるイアーゴの罵詈誹謗の言葉を受け遂にはその奸言によって愛する美しい妻デズデモウナを殺してしまいます。だが、観客はオセロウを嫉妬にさいなまれた狂人と見ず、むしろオセロウの一種の高貴さ、気品さえ感じて涙するのです。 なぜシェイクスピアはオセロウにムーア人を配したのでしょうか?次夜でそのわけを探ることにしましょう。 |
| 第468夜 - ムーア |
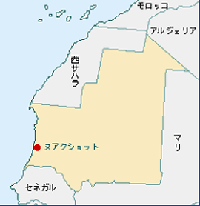 ムーア(Moor)自体についての解説は、意外に少なく OED や Britannica よりも The American Encyclopedia の方が丁寧です。それによると、現代では Maunitania, Ceylon, Philippines など種々の地域でムーア人と呼ばれる人々を指します。中世では、北アフリカ又はスペインで黒色のイスラム教徒のことでした。ムーアはローマ時代においては、現在の Algeria や Morocco に当たる Mauritania の住民を意味するラテン系の Maurus に由来し、その地域で17世紀以降イスラム教が拡がっていました。北アフリカやスペインのムーア人は明るい皮膚色でありましたが、多くの中世のヨーロッパ人達は、シェイクスピアの『オセロウ』のなかに描かれるような黒肌のイスラム教徒と考えていました。近代のMauritaniaに住む45万人のムーア人は公式にはゼネガ語(Zenaga)を話し、ハミティック語(Hamitic Language)の方言を用いるイスラム教ベルベル(Berber)人です。しかし、その多くは後にアラビア語を用いるようになりました。彼等は多くは遊牧民族で、農耕と狩猟を主にして生存しています。彼等は11世紀から12世紀にモロッコを支配しましたが、その後は政治的に目立たない存在となっています。 ムーア(Moor)自体についての解説は、意外に少なく OED や Britannica よりも The American Encyclopedia の方が丁寧です。それによると、現代では Maunitania, Ceylon, Philippines など種々の地域でムーア人と呼ばれる人々を指します。中世では、北アフリカ又はスペインで黒色のイスラム教徒のことでした。ムーアはローマ時代においては、現在の Algeria や Morocco に当たる Mauritania の住民を意味するラテン系の Maurus に由来し、その地域で17世紀以降イスラム教が拡がっていました。北アフリカやスペインのムーア人は明るい皮膚色でありましたが、多くの中世のヨーロッパ人達は、シェイクスピアの『オセロウ』のなかに描かれるような黒肌のイスラム教徒と考えていました。近代のMauritaniaに住む45万人のムーア人は公式にはゼネガ語(Zenaga)を話し、ハミティック語(Hamitic Language)の方言を用いるイスラム教ベルベル(Berber)人です。しかし、その多くは後にアラビア語を用いるようになりました。彼等は多くは遊牧民族で、農耕と狩猟を主にして生存しています。彼等は11世紀から12世紀にモロッコを支配しましたが、その後は政治的に目立たない存在となっています。 |
| 第469夜 - ムーア人 |
| 前夜の叙述だけからはムーア人のイメージはそれほど強くありません。しかし、8世紀にスペインを征服するなど、ローマやヨーロッパ人にはムーア人は、黒色あるいはかなり浅黒い(もっとも’白’ムーア人(White Moors)もいました)バーバー(Berber)とアラブの混血種としてかなり知られた存在でありました。 一方 OED による語源では、ムーア人は黒人の起源であることのほかに、Barbaryはムーア人を指すともいわれています。 しかし、ムーア人は単なる野蛮人ではありませんでした。その証拠は、種々のアフリカ史が証明しています。ヨーロッパがアフリカ社会に与えた影響は有害なものばかりであった、とローランド・オリヴァーは指摘する一方で、モール人(=ムーア人のこと。引用者)は、例えばヨーロッパの火器を「モロッコから西スーダンへ、トリポリからボルヌーへ、エジプトからセナールやダルフールへ普及させた」と記述しています*。 *ローランド・オリバー版著 『アフリカ史の曙』 岩波新書 p.179. またバスコ・ダ・ガマの航海日誌のなかには、しばしばムーア人が登場しますが、概して好意的であり、交渉或いは商売上手な種族として描かれています。例えばモール人(=ムーア人。以下同じ)の統治能力の高さを示す例として、「モザムピークの町から海岸にそって行くと、本土にすぐ近く、島が一つあり、キルワといい、その島にはモール人の町があり、わたしたちの様式をまねて、窓の多い石とモルタル造りの美しい家がたくさんあり、すばらしい建具である。町の周辺には川がいくつかあり、美しい水が流れるたくさんの水路のある果樹園やくだものの畑がある。モール人の王がそれを支配している。 (中略) この町には大量の金があった。モール人は白いのも黒いのもおり、金や絹やもめんのいろいろたくさんのぜいたくな衣服を着てりっぱであるが、また女たちも同様で、足と腕にはたくさんの金や銀の鎖と輪をはめ、また耳には宝石の付いたイヤリングをたくさん付けている。これらのモール人はアラビア語を話し、アルコラーン〔コーランのこと〕の教えに従い、マファメデ[マホメットのこと]をあつく信じている。*」などとあります。
|
| 第470夜 - ヒュームとムーア |
| 今夜はヒュームとムーア人の関係を社会思想史の観点から見ていくことにいたしましょう。ヒュームは、古代ギリシャの徳・ローマ人の礼節と、自由奔放なバーバリアンとが結びついて、新たな文明を築く姿を描きます。それは例えば奇妙なゴシック建築に現われ、最後には騎士道精神の発生に終わります。「ロマンティックな騎士道(Romantick Chivalry)・・・が、ムーア人とアラビア人から伝えられた・・・」とあるとおり、ムーア人に注目を置いているように見えます。ヒュームはムーア人自体を余り多く語ってはいませんが、モロッコにおける黒人と白人とのいわば皮膚の色だけの抗争にはむしろ害が少ないと見ています。次のような関連した叙述もみられます。 ・・・もし問題を正しく検討するならば、われわれの方がはるかに多くの嘲笑の種を彼らムーア人に提供しているはずです。・・・ ・・・モロッコの白人たちが黒人たちに迫って皮膚の色を変えることを要求したとか、あるいは、強情を張る場合には黒人たちを異端尋問や刑罰法規で脅迫したとか、という事実をわたしは知りません。また、黒人たちがその点で白人たちよりいっそう分らずやであるということもありませんでした。・・・(ヒューム『市民の国』下 p.176. p.286-287) つまりヒュームは、ムーアならびにムーア人に対して野蛮人ながら好意的であったように「ハテナ」には思えます。
|