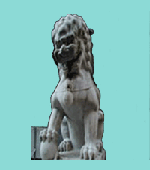前夜からの続き
|
第106夜から第110夜まで
|
|
第106夜 - 歴史とは何か
|
| 「歴史は、現在と過去との対話である」と喝破したのはE.H.カーです。もう随分前(学生のとき)に読んだ古典中の古典である、岩波新書、清水幾太郎訳の『歴史とは何か』の内容は概ね忘れてしまいましたが、不思議に以下のような事例(つまらぬところとお思いでしょうが)だけは覚えております。カーは言います。
ジョーンズがあるパーティでいつもの分量を越えてアルコールを飲んでの帰途、ブレーキがいかれかかった自動車に乗り、見透しが全く利かぬブラインド・コーナーで、その角の店で煙草を買おうとして道路を横断していたロビンソンを轢き倒して殺してしまいました。混乱が片づいてから、私たちはー例えば、警察署ーに集まって、この事件の原因の調査をすることになりました。これは運転手が半ば酩酊状態にあったせいでしょうかーこの場合は、刑事事件になるでしょう。それとも、いかれたブレーキのせいでしょうかーこの場合は、つい一週間前にオーバーホールした修理屋に何か言うべきでしょう。それとも、ブラインド・コーナーのせいでしょうかーこの場合は、道路局の注意を喚起すべきでしょう。 そこへ、ある世に知られた紳士が飛び込んできて次のように主張します。いささか長い議論になり、今夜はもう眠たいでしょうから、次の夜話で種明かしをしましょう。 |
|
第107夜 - ひき殺されたロビンソンが犯人?
|
| ロビンソンが煙草を切らさなかったら、彼は道路を横断しなかったであろうし、殺されなかったであろう、したがって、ロビンソンの煙草への欲求が彼の死の原因である、だからロビンソンが愛煙家であったから殺されたのだ、と主張します。飲酒癖でもブレーキの点検不備でも道路の改良整備でもなく、煙草のせいだと言うのです。これは普通には考えられない理由と思われるでしょう。ところが歴史には往々にしてこの種の原因をことさらに強調して曲がった解釈をほどこしてしまう、とカーは警告するのです。これと同じような有名な例は、’クレオパトラの鼻’でありましょう。もしクレオパトラの鼻がもう少し低かったら(つまり美人でなかったら)、アントニウスの征服はなくしたがって歴史は大きく変わっていただろう、というように。
歴史というものは、いろいろな事実をもとにして解釈分析が行われます。そのなかの一部分のみを取り出して強調する結果、ロビンソンのようになります。さりとて沢山の事実をしてそしてそれだけでもって歴史を語らせることもできません。偶然的な原因を一般化することもできません。歴史における解釈はいつでも価値判断と結びついている、というのが碩学カーの言いたかった点でありましょう。 |
|
第108夜 -E.H.カーの名講演
|
| 歴史は、現在と過去との対話と申しました点をもう少しカーの言葉をもって敷衍しましょう。
このような語りかけは、この著『歴史とは何か』が、もともとはカーがケンブリッジ大学での講演、続いてBBCの放送を通じて行われたためです。清水幾多郎による’ます調’での見事な名訳となって世に普及されました。到る所に名句、箴言がちりばめられています。たとえば「ハテナ博士」が好む次のレトリックなどは感心するばかりです。 ”事実というのは決して魚屋の店先にある魚のようなものではありません。むしろ、事実は、広大な、時には近よることも出来ぬ海の中を泳ぎ廻っている魚のようなもので、歴史家が何を捕らえるかは、偶然にもよりますけれども、多くは彼が海のどの辺で釣りをするか、どんな釣り道具を使うか・・・によるのです。全体として歴史家は、自分の好む事実を手に入れようとするものです。歴史とは解釈のことです。” |
|
第109夜 - 客観的な歴史
|
| とは言え、上のように価値判断を伴い、歴史家の解釈に委ねてしまう歴史になってしまうと一体歴史には客観性がないのか、と疑問も湧いてくるでしょう。かつて学生の頃習った歴史家ランケは、歴史家の仕事はただ本当の事実を示すだけである、と言って道徳主義的な歴史を批判しました。この考えは概して19世紀の歴史家たちのもので、この時代は「本当の事実を示すだけである」という魔法の言葉を呪文のように唱えることが主流でありました。ところが余りに事実、事実とばかり言いますとそれはカーによれば、歴史は「子供のイロハ並べと同じで、何でも好きな言葉を綴ればよい」ということになりかねません。ここに再び真に客観的な歴史の必要性が生まれることになるのです。カーは言います。見る角度が違うと山の形が違って見えるからといって、もともと、山は客観的に形のないものであるとか、無限の形があるものであるか、ということにはならないと言います。
したがってカーは、 「歴史とは歴史家と事実との間の相互作用の不断の課程であり、現在と過去との間の尽きることを知らぬ対話なのであります。」 と結論づけるのです。 |
| 第110夜 -権力は腐敗する |
カーに関わる物語も5夜にわたるので今夜でお終いにしましょう。最後に、アクトンについて触れておきます。皆さんすでにお馴染みのあの言葉、すなわち、
|