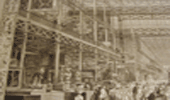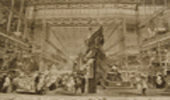前夜からの続き
|
第111夜から第115夜まで
|
|
第111夜 - 雇用者は雇い主?
|
| ある経済書の邦訳を読んでいると次のような文章に出くわしました。
・・・雇用者はそこでは、企業内部の「市場」におけるオーケストラ指揮者のように見られている。 雇用者が指揮者?変ですね。でも通常は雇用者とは雇い主のことだとほとんどの人が思っているようです。そこで経済辞典を引きますと、「雇用者」の定義は、「就業者のうち他人に雇われ報酬を受けている者」とあり、どうみても雇い主ではありません。現にその箇所を原書で見ますと The employer is thereby regarded as an orchestrator of a 'market' within the firm. この言葉の誤用はしかし、もう定着してしまっているようです。そこで「ハテナ博士」は、やむを得ず「雇い主」と「被雇用者」という用語で使い分けています。本来雇われている者に「被」と付けるのはおかしいのですが、大抵の経済書はこのように使っており、不本意ではありますが世の中に逆らえずそう呼んでいます。 |
|
第112夜 -水晶宮に象徴されるもの
|
| ヴィクトリア女王の治世(1837〜1901年)は、パクス・ブリタニカといってイギリスの繁栄を謳歌した絶頂期でありましたが、それを見事に象徴したのが、1851年に開かれた「ロンドン万国博覧会」であり、中でも総ガラス張りの斬新なデザインで見る者を驚嘆させたのは「水晶宮」でありました。そのオープニング・スピーチには次のような、人類の進歩とイギリスの国力の永続への自信が織り込まれています。
人類の営みの進歩を謳いあげるということでは、この『工業製品の大博覧会』(グレイト・エグジビジョン)ほどの意義をもつものは世界のどの歴史の記録にもない。・・・今、ここに偉大なるわがイギリス国民が、世界のすべての民を招いて、人類の文明と技術進歩の成果を世界に示すべく一大祭典を催し、その輝かしい成功を誓うものである。 下図は当時の水晶宮のスケッチで、薄暗い図書館のIllustrated London Newsの挿絵からデジカメで撮りましたため写りが悪くてご免なさい。
ところが、繁栄の絶頂期にあるまさにその時にすでに衰退の兆しが忍び寄っているというのが歴史の教えるところです。それを見事に嗅ぎつけたお話を次夜で二、三ご紹介しましょう。 |
|
第113夜 -a chill in the air
|
| イギリス経済史の大家、エイザ・ブリッグズは、1851年の大英博覧会の開催をもって、この時代を画しています。「産業の進歩を示す決定的な事実は、1851年の大博覧会(the Great Exhibition)での産業館の中で示された。それは全人類が到達した真の実験であり発展の生き生きした足跡を展示し、そしてすべての国が更なる努力を目指し得る新しい出発点を示したのである。・・・この英国大博覧会は、まさに国家の信頼を強く主張する1851年の国際主義以外の何ものでもなかった」と。しかし、同時にブリッグズはこうも付け加えたいるのです。「道徳という心地よい毛布で」労働者の困窮という社会問題をおおい隠しており、「今や、都市労働者にも選挙権が与えられたが、彼らには確かな知識もなくただ将来の政治への不安があるのみだった。・・・もうすでに午後になった、’空気は冷えている’(a chill in the air)」と描いているのです。さすがに歴史家の洞察は鋭いものがありますね。
(Aza Briggs The Age of Improvement 1783-1867 より) |
|
第114夜 -イギリス衰退の兆し
|
| このロンドン万国博覧会から27年後、外交官の眼で歴史を鋭く洞察したモーリアという人も次のように指摘しました。
イギリスの力は今や、衰微と退潮の流れに入っている。見かけは巨大な鉄甲戦艦であっても、エンジンの火はもはや消えかけており、船は舵を失い漂流し始めている と。それからまた10年後のロンドンエコノミストの編集長(モーリアー)も同じような筆法で語ります。 良し悪しは別にして、今、イギリス人の心に大きな変化が起こっている。われわれは今、自分自身に確信がもてなくなり、かつての古い考えや意見を堂々と述べるのをためらい、自分の内面が命じるところのものに自らまた疑いをさしはさむ。われわれは自分たちが誰かを統治する道徳的な正当さをもはや信じられなくなりつつあり、それには自らへの統治ということも含まれているのである。 このようにして大英帝国の衰亡の歴史が始まるのです。だが、「ハテナ博士」は今でもこう信じています、確かに世界に版図を広げた植民地の喪失、2度にわたる世界大戦による疲弊等々パクスブリタニカの勢いは失われましたがイギリス人の精神は決して衰亡していないと。 これを論じていきますと延々とイギリス論が続きますので、いずれ機会がありましたら第何夜かで取り上げることとして話題を変えることといたしましょう。 (参考:中西輝政『大英帝国衰亡史』より) |
| 第115夜 -悪が勝つ理由 |
|
お話は変わりますが先日、DVDで映画「ティアーズ・オブ・ザ・サン」を見終わったとき、最後のテロップに次のような英語が流れていました。
この映画が名画かどうかは判りませんが、エドモンド・バークといえば英国きっての政治社会思想家です。このバークの言葉が引用されていることに驚きました。この映画は、アフリカはナイジェリアの内戦で孤立したアメリカ人の女医を救出する命令を受けた特殊部隊がその命令に反して病気に苦しむ現地の難民をも助けようとする筋書きでした。命令どおり同国のアメリカ人だけを救出するだけでは本当の善き事ではないと部隊の長は決意するのです。このDVDには日本語の字幕がでていましてその訳は次のとおり 「善なる人々が行動を
|