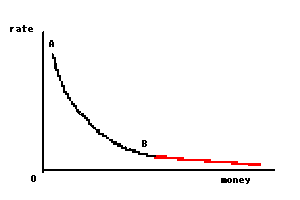前夜からの続き
|
第136夜から第140夜まで
|
|
第136夜 - 統計の数値ということ
|
| 今、数(numbers)という学問領域が呼び起こされているんだそうであります。手っ取り早く言うなれば、事実というものを正しく数によって掴めることができるかどうか、ということでありましょう。数は必ずしも絶対的なものを表象するものではありません。例えば身近な複式簿記をみてもいろいろなルール付けがあって、フィクシィアス(fictitious)な数値がやむなく存在しますが、これを発明、普及させた(イタリア)ことは正に数量革命といえるでしょう。 統計学の父と言われるウィリアム・ペティは、一国の富の大きさを何とか数字で示そうとしました。たとえばイギリスはフランスよりも国土は狭いのに富は大きい、当時のオランダ(17世紀)はイギリスよりも豊かであった、領土はイギリスより狭いのに。これを数字で表したいという思いで「政治算術」「租税貢納論」を書きました。 現在でも、一見不思議なような取り決めが行われています。生命保険料が統計上貯蓄に入るのは何となく判る気がいたしますが、住宅ローン返済のために月々支払うお金も貯蓄に入るのは合点がいかないでしょうね。統計上では負債が減る=貯蓄というふうに考えるのです。とすれば借金が増えて貯蓄増大ということになりますね? |
| 第137夜 - ヘリコプターからお金を撒く | |||
| デフレを払拭するためにはあの手この手の金融緩和政策がとられていますが、いずれもうまく機能していません。そこでいっそのこと貨幣を市中に直接ばらまけば、という突飛な案も出ています。ヘリコプターマネーと言われるのがそれです。冗談じゃないよ、とおっしゃるかも知れませんが、堂々と?経済学の教科書に載っているのですからあながち空想の産物とも言い切れません。 その意図するところはこうです。ヘリコプターマネーのように貨幣をばらまけば物価が上がる。そうすれば減税や公共支出などの財政支出を金融政策でファイナンスするのと同じ意味になるのです。財政政策を金融政策でファイナンスする、というのが本当の意味で、文字通り本当に空からお金をばらまくというのではありません。このレトリックを使ったのはM. フリードマンだったっけ。あちらの人は喩えが上手いですね。問題は財政政策を金融政策でまかなうということが、政府の発行する国債を日銀が直接引き受けるということになり、現在は禁じられていますが、いつかきた道(軍部の圧力により日銀が直接引き受けて戦争、インフレに至った道)をたどることになり兼ねません。因みに現在の日銀は市中に流通している国債を金融機関から購入してベースマネーを供給しています。 |
|
第138夜 - 流動性の
|
| 現在の日本はゼロ金利という異常な状況にあります。どうしてこういうことが起こるのでしょうか。下図を参照しながら簡単に説明いたしましょう。
縦軸に金利を、横軸に貨幣量をとった図では通常は右下がりの曲線(AB)で描かれます。これを貨幣需要曲線といいますね。つまり金利が低くなるほど貨幣需要が増える、ということで納得できますね。ところが問題は、この貨幣需要曲線が水平に近くなる点、図でいえばBより右側で金利がゼロに近くなる部分です。このような状態になりますと、貨幣量が大幅に増えてももう金利はわずかしか下がりません。この部分が「流動性の罠」といわれるのです。この罠に落ち込んでしまえば貨幣量をいくら増やしても金利はほとんど動かない、つまり金融政策が効果を発揮できなくなる。この点を衝いたのがケインズでした。
|
|
第139夜 - 生活必需品に高い税金を掛ける?
|
| 経済学では通常考えられているのと逆の発想をするものです。生活必需品には高い税金を何故掛ける!? 逆じゃないのか、とおかんむり。でも実際にそれを提唱した人がいます。F.ラムゼイという人の最適税(optimal taxation)の考え方です。このラムゼイの考えを高く評価したのが、かのケインズです。この若き天才数学者はラムゼイルールとして知られる最適税を提唱したのです。一言でいえば、需要や供給の価格弾力性の低い財やサービスに、より高い税金を課すのが望ましいと言うものです。反対に需要の価格弾力性が高い奢侈品には高い税を課さない、ということになります。こんなことってまかり通るのか!! その理由はこうなのです。資源配分が大きく歪んでいるとき(実際はその通り)には資源配分の歪みをもっとも少なくするような税体系が望ましいのだ。つまり生活必需品に高い税を掛けることによって価格が高くなっても経済主体の行動には大した変化はなく需要の減少もない。そうするといずれも需要は落ちない。でも、奢侈品に低い税を、必需品に高い税を、というのでは、分配の公平からみてとうてい国民の合意は得られないでしょう。でも理論としては筋が通っている。こんなところにも経済学が役に立つ、立たないの論議が起こりそうですね。 |
| 第140夜 - そのあとが怖い |
|
お客様の文句やクレームは決して一過性ではありません。否、それどころか予想する以上に増幅するものです。少し古いですがこんな調査がありますので紹介しましよう。
あなたの店で顧客がなにか不愉快な思いをしたとしても、27人のうち26人までは、その苦情を店に申し出ないということだ。・・・・・・店に文句をつけてみたところで、どうせ満足な対応は得られないと思っているからである。だが、そのあとが怖い。店に不満を抱いた客のざっと91パーセントは、二度とその店を訪れようとはしない。さらに怖いことには、この店を見限る者のパーセンテージは、わずか1ドル79セントの品物を買う客にも1000ドルの買い物をする客にも、ともに当てはまるということだ。そして、たぶんなにより悪いことに、いったん腹を立てた客は、平均して9人から10人の仲間にその話をする。しかも、そのうちの13パーセントの者は、20人以上の人びとに吹聴して回るのだ。 (トム・ピーターズ:『経営革命』より) |