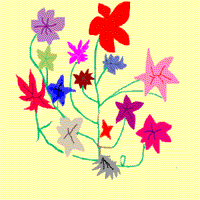前夜からの続き
|
第171夜から第175夜まで
|
|
第171夜 - 教わる能力
|
|
お年玉付き年賀状も当選が決まりもう整理整頓されたことでしょう。年賀状には極く短いスペースながら、はっとするような箴言が込められたものがあります。「ハテナ」の場合、一番忘れられないのが、或る先生からの言葉でした。”学ぶということは、教わる能力が要るものです。この点私などは年がら年中教えてばかりいて、教わる術を持たずに来てしまいました”というような主旨でした。つまり、教わるということは能力がなければできないんだよ、という励ましのメッセージなのです。 これに関連して思い出されるのがマイケル・ポランニーの言葉です。折角高尚で重要な知を教えようとしても聴く耳を持たぬ者に対してはその知は何の役にも立たぬ、というようなことを言っていたと記憶しています。参考文献が手元にないのでちょっと正確な表現ではないかも知れません。これもそれこそ読む能力のない「ハテナ」の誤読かもしれません。 そこで「ハテナ」は新しい発見をしました。巨匠の演ずる音楽会は何万円もするのにそれを聴く耳をもたぬ者には猫に小判。それよりも学生たちが部の活動で演奏する音楽会で充分。(学生達には失礼!)第一安い。それに一生懸命に演奏しているし、直前になってもチケットも手に入る。でもって大学部のオーケストラを結構楽しんでいます。 (参考:マイケル・ポランニー『暗黙知の次元』 ちくま学芸文庫) |
|
第172夜 -労働が先か効用が先か
|
| ものの価値を決めるのは、人が働いた労働にあるというのが古くからある古典派経済学の基礎にある考えでした。ところがそうではないその物の価値は、人がそれを求めようとする効用にある、といって新しい学説を打ち立てたのが効用価値説、その発展として限界効用学派です。世はこれをもって「限界革命」と名付けました。つまり費用(労働)説から効用説への流れの転換をもって革命(パラダイムの転換)と捉えたのでした。
ところがこの効用説は労働費用説よりも以前に、或いは同等に唱えられているのです。それは古くはアリストテレスにまで遡ります。アリストテレス以来、価値が欲望の度合いによる主観説と生産費に基づくという客観説とが対立してたのでした。しかし、現在は効用に基づく学説が主流のようです。この意見によりますと、こうなります。 「ハテナ」にはどうもその論理(原因ー結果論)が良く判りません。やっぱり生産費を賄うに足る物の値段が付けられるのがオーソドックスな考え方だと思うからであります。欲望(需要)が大であるから物の値段が上がるという現象は当たり前に見られていますが、果たしてそうなのか、という問題は、価値(論)を巡る根源的な考えを確かめるのに最も大切な問題提起といえましょう。 |
|
第173夜 - 疎外ということ
|
|
今まで疎外ということの経済学的な意味は、生産との関係で理解されてきました。例えば分業によって人間はみずからの生産のなかで自己を見失ってしまうことを疎外と言ってきました。分業は物のある一部しか担当せず、それがどんな完成品として表れるのかも知らずに単調な作業の繰り返しになって自己を失っていくといったように。ところが今日のように技術が極度に進んで来ますと今度は技術そのものが人間の自己性を見失うことになります。自分の世界は、技術によって自分の視野から消えていきます。そして不毛となったり、卑俗化もされていきます。コンピュター、特にインターネットの世界でそれを痛感するようになりますね。メールを送信する相手が誰だか判らず、誰から送信されてきたのか見えない世界、そこで疎外感を感じるようになります。 (参考:ジャン=マリ・ドムナック『野生人とコンピュータ』) |
| 第174夜 -ヨーロッパ統合-その理念と現実 |
|
1991年にマーストリヒト条約(欧州連合条約)が合意されてから、14年が経ちました。実際に単一通貨として導入されたのは1999です。当初は銀行口座振り替えだけで利用され、2002年からユーロ紙幣が流通するようになりました。スタートしたときの当時の外電は、「ユーロは現実になる。単一通貨は、平和と繁栄に基づいた共同体建設の象徴となるだろう」と伝えました。当時は、あの歴史的な役割を果たした強いマルクへの郷愁から、旧ナチの地下要塞にマルクを集めて保存しようという動きもあったそうですが、毅然として廃棄してしまいました。あの強いマルクを守ったドイツの中央銀行ブンデスバンクもEU地域内の一中央銀行に過ぎなくなったのです。「花咲き誇る田園」「物質的生活条件の可能な限り完全な平準化」という理想主義はどう達成されていくのでしょうか。
現在は順調に機能しておりますが、「ハテナ」には次の2点が、課題として今後に残されているように思われます。 ① EU15ヵ国(現在は11ヵ国)を束ねる政策決定過程における民主主義的手続きはどうなっているの? 民主主義的多数決ルールは機能するであろうか、という問題です。特に迅速をせまられ、かつ各国の同意を得るという話し合い、根回しはどのようにして行われるのでしょう(欧州議会には完全な立法権は付与されていません)。そのような手続きの煩雑さは民主主義の欠陥とされ或いは民主主義は高くつく、と云われる所以なのです。 ② 金融政策と財政政策との間に矛盾を来すことはないの? EU各国は自国の通貨主権を放棄しユーロに統一しましたが、財政政策は各国の主権を残しています。金融政策のみをESCB(欧州中央銀行制度)に移譲するという金融の一元化と、各国の主権を認める財政の多元化との間に不一致の発生する恐れはないか、という疑問です。 このような当初に抱かれた疑問も現在では特に顕著に表れていないようです。EUは確実に根付いてきたと見るのが大方の見解でしょう。しかし「ハテナ」には以上の2点が今なお気にかかります。そうした事態が出現しないことを願いつつ。 |
|
第175夜 - 市場経済における投資
|
| 今日の市場経済における投資行動は、一種の「ばば抜き」ゲームのようなもの。それを充分承知のうえでいわゆる玄人の投資家は、熟練すればするほど「仲間を出し抜き」、群衆の裏をかいて価値の下がった通貨を他人につかませる。 アメリカの経済学の大家ハイルブローナーはこのことをゲームに喩えて次のように言っています(「ハテナ」はアメリカのゲームをよく知りませんがそのまま引用します)。 長時間にわたる投資の予想収益を予測するよりむしろ、2, 3ヵ月先の慣行的評価の基礎を予測しようとするこの虚々実々の戦いは、玄人筋の胃袋を満たすために大衆の中に鴨のいることすら必要としない-その戦いは玄人筋同士で演ずることができるからである。また、評価の慣行的な基礎は真の長期的妥当性をもつという単純な信念を抱いている人がいることも必要ではない。なぜなら、それは言ってみれば、スナップとか、オールド・メイド(ばば抜き)とか、ミュージカル・チェア(椅子取りゲーム)に似た遊戯だからであるーこれらの遊戯では、遅くもなく早くもなくちょうどよい時に「スナップ」と叫んだものとか、遊戯の終わらない前にばばを隣の人に手渡したものとか、音楽の止まったときに自分の椅子を確保したものが勝ちとなる。遊戯しているものはみな、手から手へ回されているものが「ばば」であることを知っており、また音楽の止まったときに遊戯者の中のだれかは座る椅子がないことを知っているにもかかわらず、これらの遊戯は面白おかしく遊ぶことができる。 (ロバート・ハイルブローナー『私は、経済学をどう読んできたか』) |