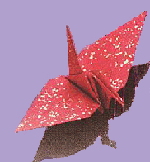前夜からの続き
|
第191夜から第195夜まで
|
|
第191夜 - エイジェントとプリンシパル
|
|
一般に市場取引では、その中で交換(売買)される商品の品質は一定で売買の当事者も誰であるかに関係なく、取引される価格のみが問題とされます。ところが企業や当事者の組織のなかでは、このような均質な対象を扱うとは限りません。取引相手ーこれをエイジェントといいますーがどのような行動にでるかわからない場合があります。この場合に当の本人ーこれをプリンシパルといいますーはどのような利益を受けるかが判りません。取引者同士のこの関係をエイジェンシー関係といいます。その主な例を以下に掲げておきます。古典的な市場観ではなかなか律しきれない問題が現代の複雑な経済に表れる例といえましょう。
(参考:根岸隆編『経済学のパラダイム』より) |
|
第192夜 -連続か断絶か
|
| 経済に限らずある考えが根本的に変わることを科学革命といったり、パラダイムの転換といわれたりします。しかし一体何が契機でこのような革命や転換が起こるのかについては見方が異なります。一方は、科学の本質を反証による絶えざる革新の過程とみなすもので、常に新鮮な変革への志向を持っていることが科学の進歩に不可欠な条件だと考えるのです。これを連続的革命史観といいます。他方は、パラダイムの交代は断続的な革命史観によって起こるというものです。もしそれが連続的に行われるのであればそれは革命的とはいえない、新しい考えが断続して起こるからこそ革命といえる、というものです。経済学における革命は例えばアダム・スミスによる古典派経済学、限界革命、それに何といってもケインズ革命がその代表的なものでありましょう。 |
|
第193夜 - 雲と時計
|
| 「雲と時計」という何とも奇妙な論文を書いた人は、カール・R・ポパーです。「雲」はいわし雲や積乱雲のようにその時その時で形や大きさが異なります。元は単なる水蒸気の集まりなのにどうしてこうも形状不安定なんだろう?分子の集まりに一定の法則なんてないようです。これに対して「時計」は一定の歯車の原理で正確に時を刻む構造になっています。「雲」は今日の言葉でいう複雑系の現象、これに対し「時計」はニュートン的世界といえるでしょう。ところが永らく君臨したニュートン的世界に住む学者は、”すべての雲は時計であるーもっとも雲的な雲でさえもが”と物理的決定論を唱えます。これに対しポパーは彼らを批判します。これはニュートンが間違っていたのではなく「雲」を扱っていなかっただけで、これを後代の物理学者が雲を時計的に分析しようとしたせいだと。そうすると「ソフト」に制御された「雲」のような現象はどう理論づけられるの?と第二の疑問が出ます。「ハテナ」の乏しい知識ではポパーはそれに的確に答えてはいないようです。
(参考:ポパー『客観的知識』) |
| 第194夜 -進歩と進化はどう違う? |
| 17世紀後半から18世紀の啓蒙思想の時代には、歴史の法則は自然の法則と同じものだと考えていました。また一方同時代人は進歩ということも信じていました。ということは自然も当然進歩すると思っていたのです。ところが、自然は当然には進歩するものではありません。後の時代になってヘーゲルのような人は、歴史を進歩するものとし、進歩しない自然と区別しました。これに対してダーウィンは、進化と進歩を同一視した考えを持っていたといえます。しかしこの考えは進化の根源である生物的遺伝と歴史における進歩の根源である社会的要因とを混同することになります。ヨーロッパ人の赤ん坊を中国の家庭に預けたら、この子供は皮膚は白いが中国語を話す人間に育ちましょう。皮膚の色は遺伝であり、言語は人間の脳髄を通ずる社会的獲得です。遺伝による進化は何千年、何百年、或いはそれ以上とかの単位でしか変化しませんが、獲得による進歩の方が早いのです。その意味で歴史というものは、獲得された技術が後世に伝達されていくことによって進歩するのです。
(参考:E.H.カー『歴史とは何か』) |
|
第195夜 - 陰鬱な科学(ディズマル・サイエンス)
|
| 経済学を、「個人を純粋に利己的で利欲的な動物と見、国家をたんにそういった動物の集塊と見なした」陰鬱な科学から解放したのは、アルフレッド・マーシャルでありました。彼は『経済学原理』を送り出し新しい経済学の到来を告げた人でした。ケインズはその師であるマーシャルを古典派経済学の最後の人と批判的に位置づけながらも、彼を次のように称えています。
「マーシャルは古来最初にして最大の、生粋な経済学者であり、初めてこの学科を、それ自身の基礎の上に立ち、科学的正確さにかけた物理学ないし生物学にも劣らぬ高い水準をもった別個の科学として樹立するために、その生涯を捧げた人であった」。 上で経済学を陰鬱な科学と表したのはカーライル(Thomas Carlyle 1795-188)で、当時マルサスの人口論が話題になった頃のことで、こんな経済学を Dismal Science と呼んだのでした。 (参考:ケインズ『人物評伝』) |