| 第11夜-ギュフェンカーブ |
| 事の起こりは1845年のアイルランドの飢饉に始まります。この地方の主食はジャガイモで、その価格は高騰しました。でもアイルランドの家庭ではジャガイモの消費を減らすどころか前よりも一層多くのジャガイモを買うということが起こりました。普通経済学では価格が上がると需要は減り、下がると需要は増えると教えます。でもこれは反対の現象ですね。なぜでしょうか? 飢饉に遭った貧しい消費者は、他の高価な食品、例えば肉を減らしてジャガイモに切り替えるからです。普通はジャガイモが高価になると他の安い品に切り替えようとします(これを代替効果といいます)。しかしジャガイモのような生活必需品ともなれば他の品に切り替えることができません。むしろ所得が減ると高値な品物を減らすことによって(ここでの例は肉です)比較的に安価なジャガイモが却って増えるという現象が発生します。
ギュフェンカーブ 価格 この事例を最初に指摘したのはヴィクトリア時代の経済学者であったフランシス・ギュフェンで、彼の名に因んで下のような曲線をギュフェンカーブと呼ぶようになりました。 (参考:サムエルソン『経済学』) |
| 第12夜-缶詰のお話 |
| 今夜のお話は、他愛もないブラックパロディで、お読みになってお叱りを受けるかもしれません。あらかじめお断りさせていただきます。
物理学者と化学者と経済学者の3人が船の難破で無人島に辿り着きました。生憎ボートの中には缶詰しかありませんでした。上陸した3人は、何とかして缶詰を開けようと知恵を絞ります。物理学者は太陽光線の照射を利用したり、石でもってこじ開けようとしましたが、うまくいきません。化学者は海水による酸化でサビさせようとしましたがとてつもなく時間がかかってしまいます。さて、経済学者はどうしたでしょうか?彼はいとも簡単にこう言います。”ここに缶切りがあるとせよ、そうすればそれを使って開けることができる”と! この作り話は、経済学者が到底現実でない「仮定」を置いてしかも物凄く精緻に理論を立て、その仮定が正しいか、現実的であるか、を一向に問題としない、ことをひどく皮肉ったパロディでした。 よく経済学は現実を説明しない、だから役に立たない!と言われるのは、案外このパロディのようなことが生じているのかも知れませんね??? |
| 第13夜-事実判断と価値判断 |
| その事実が正しいか間違っているかを判断する(事実判断)ことと、ある事が望ましいか望ましくないかを判断する(価値判断)とは、明確に区別されねばならない、ということが長い間の定説でありました。
ところがそれがどうも見分けがつけられない、という風に言われだしたように思えます。例えば、今わたくしがはめている腕時計は極めて安物ですがこれが一番正確に時を刻みます。とすれはこの時計は良い時計であると言えるでしょう。つまり正確という事実が良いという価値判断を生むことになります。また潜水艦の艦長は全責任をもっておりますが、潜水中の事故発生の場合は、艦長の判断で一切の指揮が行われます。このような場合には事実判断と価値判断とが全く一瞬にうちに求められることになります。さらに、よく収穫を挙げる農夫は良い農夫とわたしたちは判断しますよね。 殊に益々複雑していく現代の世界では、事実と価値との区別が見極められないような諸現象に出くわさざるを得なくなるでしょう。それでも伝統的な事実判断と価値判断を区別することが必須の真理でありましょうか。経済問題に限らず、現代の哲学者や思想家を悩ませる問題がいま、目の前に突きつけられているように思われます。 (参考:マッキンタイア 『美徳なき時代』) |
| 第14夜-技術の復讐 |
| 普通技術という言葉は、「応用科学」という意味で使われています。ところが経済学者の用いる技術は、これとは少し違った意味を持ちます。技術の変化という場合は、経済学的には生産に投入されたものとそこから出てくる産出の関係の変化を意味するのです。
このことから次のような変なパラドックスが生じます。たとえば、メーカーが現場の作業員に「権限を委譲」した結果、品質が向上し、管理職の数を減らせるようになったとしますと、経済学ではこれを、技術が向上したと考えるのです。そうしますと、技術革新は管理者の雇用を不要にします。アレッ!技術が管理者をクビにする? 逆に管理者を増やして監督を強化して生産量が増えると技術は向上し、管理者の雇用は安泰です。一体どちらがいいの? わたしたちの手じかにある例では、真っ先に持ち出されるのはコンピュータでありましょう。コンピュータのオペレーターが1人いれば、タイピストが6人要らなくなるという例はよく挙げられます。しかし他方でコンピュータが普及したからといって、弁護士や医者、企業幹部の需要は増えません。ということは技術というものは、直接働く人にとって代わるというのではなく、技術が一部の人の力を増幅させるのだ、ということなのです。 そうすると技術というものは、少数の幸運な人に有利に働き、その他大勢には不利に働く、技術がいわゆる「勝ち抜き戦」の様相を強めるものなのでしょうか。H.G.ウェルズは『タイム・マシン』(1895年)のなかで、労働者が人間以下の地位に落ちる未来世界を描きましたが、外れてしまいました。労働者の賃金は結構上昇し、今日では国民所得に占める資本所得の割合が低下し、労働所得の割合がむしろ上昇しているのです。 技術の知的能力と才能を持つ人のことを「シンボリック・アナリスト」(ロバート・ライシュ)と呼ばれていますが、しかしごく普通の人でも、スーパー・コンピュータもはるかに及ばないほど、あいまいな情報処理をこなしておりますよね。”1956年のプログラムでは、計算問題が解けた。61年のプログラムでは、大学レベルの数式が解けた。70年代になってようやく、ロボットのプログラムがつくれるようになった”が、”子供が積み木を積み重ねる程度の認識能力と制御能力しかもたなかった”と(人口知能の提唱者M.ミンスキー)。 結局、人間になくてはならぬ仕事というものは無くならないといえそうです。例えば、完全自動化工場の掃除はいったい誰がするの?庭の手入れは?等々、不自然なことは機械にやらせ、自然なことは人間に残される、というのが将来の理想の姿でありましょう。それにはわたしたちの技術や労働の価値観が変わらなければなりませんね。 (参考:ポール・クルーグマン『良い経済学悪い経済学』) |
| 第15夜-昔の人は言いました |
| 古代ギリシャにトラシュマコス(Thrasymachus)という人がいて、こんなことを言っています。
① 正しい人間と不正な人間が共同で事業を行うと、正しい人の方が決まって損をする。 ② 国に献金しなければならないときには、不正な人は少なく済ませる。 ③ 国や公共体から分配に預かるとき、不正な人はしこたま取り込む。 ④ 何らかの役職につくとき、不正な人は他人を制して大きな利得を手にいれるが、正しい人は役立たないとして嫌われる。 ⑤ 不正な人の究極の存在は僭主であるが、彼は国民からもよその国からも幸せな人、祝福された人と呼ばれる。 これって、何だか今の世界に似ていませんか。遥か昔の古代ギリシャの哲人はすでにこんな皮肉を言って、正義は強者の利益、不正は得、と難じているのです。 (参考:白石正樹「古代ギリシアの政治思想」藤原安信ほか編『政治思想史講義』) |
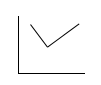 数量
数量