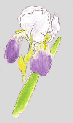|
第56夜から第60夜まで
|
|
第56夜 - 鸚鵡(おうむ)も経済学者になれる?
|
「ハテナ博士」が初めて経済学を学んだのは、ウン十年前のこと(歳がばれるから正確には申せぬ)。その時の教科書はP.A.サムエルソンの『経済学』第6版でした。現在12版を重ねなお人気を保っています。中身はすっかり忘れてしまいましたが、奇妙に次のたとえ話だけが頭のなかに入っています。
要は、経済学では需要と供給の理論が何よりも大切だということ、だから毎日のように需要、供給と呪文を唱えるようにしっかりと覚えなさい、というサムエルソン独特のユーモアと皮肉を込めたセリフだと解します。ついでに同じ箇所でマーシャルについてもジョークを引いていますが、これは翌夜で。 |
|
第57夜 - マーシャルのジョーク
|
前夜に引き続き、今夜は同じサムエルソンから、マーシャルの言葉を。
あの謹厳そのもののマーシャルにもこんなユーモアもあったんですね。 |
|
第58夜 - 燈台の経済
|
| 燈台?もしかして東大のワープロ転換ミス?いやそうではありません。ロナルド・H・コース(1991年ノーベル経済学受賞者)という人が「経済学のなかの燈台」(The Lighthouse in Economics)という面白い論文を1974年に書いています。古典的な経済学では、航海の安全のために、燈台を建設したりそれを保全することは政府にとって固有の任務であると言われてきました。つまりそれは公共的なサービスであって私企業に任せることは妥当でない、というのが通説でありました。
ところがコースという学者は見事にこの定説をくつがえしてしまいました。彼は英国の燈台制度をくわしく調べそれが水先案内協会などによって、船主から支払われる燈台使用料を積み立てた基金から費用が賄われたこと、その収入は費用に十分見合って確保されていたこと、燈台の建設も私人によってなされ、表向きは公共の利益を装いつつ実のところは私的利益を目指す典型的な投機家であったことさえ指摘したのでありました。水先案内協会のもとに管理され、何故政府の直轄としなかったか、その理由はそうした方が燈台使用は安くすむからだとコースは言います。逆に燈台業務のような公共財が一般税から賄われると管理やサービスは非効率化するというのです。コースは主張します。多くの経済学者の信念とは逆に、燈台サービスは私企業による供給が可能であると。 これって、今日のどこかの民営化議論に似ているように「ハテナ博士」は思うんですが・・・。 |
|
第59夜 - ユートピアとディストピア
|
| ユートピア(Utopia)の世界は、それが決して実現されないがゆえにユートピアのユートピアたるゆえんがある、とはかつて誰かから聞いた名セリフだと思ったことがあります。そうですね、桃源郷などに憧れてももしそれが実際にあったとしたら、それはもう桃源郷ではないものね。
さて、そのユートピアで有名なのは、トマス・モアが1516年に「ユートピア」という作品をイギリスで発表して以来のことでした。この言葉の語源はじゃな、エヘン!と、「ハテナ博士」は威張りたいところですが、実は借りてきた話。ギリシャ語から作られた造語「どこにもない国」という意味だそうです。そのユートピアという国のモアは自分の理想とする世界を描いたわけです。 反対に、このユートピアにたいしてディストピア(Dystopia:暗黒郷)がある。この世界をあらわす作品には、ジョージ・オーウエルの「1984年」やオルダス・ハックスリーの「すばらしい世界」(ちっともスバラシクなんかない!)などがありますね。ユートピアが実現不可能な世界だと「ハテナ博士」は思うのに「ディストピア」は下手をすると直ぐに陥ってしまう。たとえば、アフリカの飢餓、イラクなどなど・・・。 こう考えると人間の営みなど容易に進化しないものだと嘆きたくもなります。もっとも今流行の進化経済学などでは、エヴォトピア(Evotopia:学習により知識や制度が進化する世界)などという造語が生まれていますが・・・。 |
|
第60夜 - IBMのいわれ?
|
| 本当かどうかは判りません。IBMは、” I’ve Been Moved ” (私は異動した)の略なんだと。真偽のほどは不明、でも絶えず管理職の人間を動かしているようです。そのわけは、何もIBMにかぎらず(シティコープやモルガンでもそうだといわれています)、こうした会社がさまざまな分野で経験を積んだリーダーを育てるために、管理職の人間をラインからスタッフへ異動させたりし、そのために掛かった費用は意に介さないという点がすごいなあ〜と思うのは今の日本の企業ー専門職に固定したり、異動を制限してコストを減らそうとするーに比較するひが目からなのでしょうか?
(ウオータマン『超優良企業は革新する』より) |