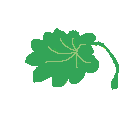前夜からの続き
|
第81夜から第85夜まで
|
|
第81夜 - 101羽目のカラスは何故黒い?
|
| 今ここに100羽のカラスを見て全部が黒い色をしておりました。とすると101羽のカラスも当然黒い筈と誰もが思うでしょう。ところがどうやって101羽目のカラスが黒いことを証明できるの?と問われるとき、やっかいな問題が生じます。そんなこと判りきっているじゃないか!100羽が黒いのなら101羽目のカラスも黒いのさ、と応える人は、経験的なものの見方や帰納法的、或いは心理的な解法の持ち主です。ところが論理的な証明にはなっておりませんね。帰納的な推論(101羽目のカラスは黒い)を正当化する合理的な根拠を見つけることは不可能に近いのです。
この問題を最初に提起した人は、ヒューム(David Hume, 1711-1776年)という人でした。以来今日に至るまでさまざまに論議されてきて今なお解決をみるどころか、「ヒュームの懐疑主義」として生き続けているのです。 |
|
第82夜 - 逆選択とモラルハザード
|
| 逆選択はadverse selectionの訳です。他方モラルハザードmoral hazardの訳は’道徳的陥穽’などと言ってややこしい。したがってここではモラルハザードをそのまま用いましょう。どちらの用語も保険の理論に由来しています。これが経済学の分野で随分と使われるようになりました。
逆選択というのは、事故の生ずる確率の低い人(丈夫な人、安全運転に徹する人など)が加入した保険から脱退するとします。保険会社は平均的な事故確率にもとづいて保険料金を算定しますから、健全な人が少なくなりますと事故発生率が高くなり保険料金を引き上げなければならなくなります。こういった現象を逆選択と言います。 モラルハザードというのは、保険に加入している者は加入していない者に対して事故に対する注意を怠りがちになります。被保険者が社会的に望ましくない誘引を与える(その最も極端な例が保険金殺人事件です)ことにより保険会社にとってリスクを高めることになります。 こうした保険理論の考えを経済学にも適用できるとしてこれらの用語は最近脚光を浴びるようになりました。次夜でお話することとしましょう。 |
|
第83夜 -金融取引への適用
|
| 前夜の議論を例えば金融取引に適用するといたしましょう。
いま、個々の借り手が持つ投資プロジェクト、例えばA, B, C・・・があるとしましよう。Aから順に有望なプロジェクトに並べてみます。この場合、有望な投資プロジェクトAをもつ借り手とより劣った投資プロジェクトB,C・・・を持つ借り手を、貸し手の方で見分けられるとは限りません(それが出来れば不良債権があんなに発生することはありませんよね)。そのため貸し手がリスクををカバーするために約定平均金利を高めに設定するといたしましょう。そうすれば有望な投資プロジェクトをもつ優良企業は、そんな高い金利では借りませんといい退出していきます。貸し手は残ったB,C・・・のリスクを考えさらに高めに金利を設定します。今度は第二に有望な企業Bはその金利ではいやだといって退出していきます。こうして次々と有望安全な借り手が消えていくという現象を逆選択といいます。 今度は一つの企業(借り手)が複数の投資プロジェクトA, Bをもつ場合を考えてみましょう。Aの方がBよりも安全な投資、逆にBはAよりハイリスク・ハイリターンであるといたしましょう。貸し手は安全な投資には低い金利を、よりリスクの高い投資には高い金利を設定するのが合理的な行動でしょう。そうすると借り手の企業はより安全なAプロジェクトを貸し手に提示して安い金利の提供を受け、その資金をハイリスク・ハイリターンのプロジェクトBに回すかもしれませんね。このような借り手はモラル・ハザード的な行動をとったといえましょう。 さて、貸し手はこれらの企業行動に対してどのように手を打てばよいのでしょうか。次夜でそれを解明いたしましょう。 |
|
第84夜 - 情報の非対称性
|
| 結論からいいますと、借り手側の行動を貸し手側がよく見究められないという点にあります。これを借り手と貸し手間に”情報の非対称性”があるといいます。逆選択のケースは個々の借り手が有する投資プロジェクトの優劣を貸し手の方で完全には知りえないという”情報の非対称性”、一方、モラルハザードでは、貸し手が貸した資金を借り手が何に、どのように使うかを貸し手は完全に把握できない、という”情報の非対称性”に起因するものです。
このような”情報の非対称性”という用語は”不確実性”と共に、経済学のキィワードとして最近特に注目され、それを主とした「情報の経済学」や「不確実性の経済学」のような分野での発展を見るようになりました。 |
| 第85夜 -市場の失敗 |
| わたくしたちが当たり前のように市場々々と呼び慣れている「市場」とはどのような条件が揃ったとき市場といえ上手く機能するのでしょうか。一般に次のような条件が備わるとき市場機構は効率的であるとされています。
①すべての財・サービスは市場を経由して取引されるー市場の普遍性 ②生産技術が分割され規模の経済も存在しない(独占がない)-収穫逓減性 ③完全競争下にあるー市場の完全性 ④情報が完全で不確実性がいっさい存在しないー情報の完全性 実際にはこのような完全な市場なるものは存在しませんよね。植草益氏はこのような想定を次のように表現しています。「このようにきわめて理論的に純化した市場状態が存在するときには、経済のなかに調整機能を果たす主体が存在しなくても、価格が需要と供給を調節するパラメーター機能を果たして、経済資源の配分を効率的な状態にする」と。 でも、現実の市場は上のような諸条件を満たしていませんね。何らかの条件の相違が需給関係に影響し、競争的な均衡価格が達成されないうえに、市場外での経済外的な要因が市場に影響を与えることがあるのです。これらを総称して「市場の失敗」と呼んでいます。 (参考:植草益『公的規制の経済学』) |