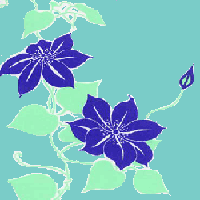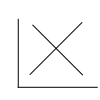前夜からの続き
|
第91夜から第95夜まで
|
|
第91夜 - アフリカの貧困
|
| 「ハテナ博士」の好きな作家の一人に、帚木蓬生がいます。この方は自ら精神科医として診療を続けるかたわら、医療をテーマにした大作を送り出しています。2004年7月に出版された新作『アフリカの瞳』は、アフリカの貧困と病をリアルに描いてズシンと来るものがありますが、そのなかでの次の言葉はアフリカの開発に対する先進諸国の姿勢を反省させる重みを持っています。
<アフリカに宣教師が来たとき、彼らは聖書を持ち、我々は土地を持っていた。彼らが祈りましょうと言い、我々に目を閉じることを教えた。あとで目を開くと、我々の手には聖書があり、彼らの手には土地があった> |
|
第92夜 - もう戦争はいや!
|
| 政治学者のアクセルロードという人は、戦争状態にある兵士の心理を次のように記し、これを経済学者は「ゲームの理論」の適例だとして引用しています。アクセルロードは、戦争時の兵士の日記を調べると、「あまり激しく戦闘をすると相手からより激しく攻撃されるので困る」というような兵士の気持ちが記されているそうです。この記述には、戦闘が継続すると、、いま自分が相手をあまり強く攻撃すると将来仕返しをされるので、できるだけ穏便にすませたいという兵士の願いが出てくるというのです。これを経済学的に表現すると、「協力的な解」への願いが込められていると言えましょう。第61夜から第69夜にかけて「ゲームの理論」を紹介しましたが、そのような協力解を求めるという分析に化けてしまうのです。(経済って何でもこのように解釈してしまう!けしからん)と言うなかれ。戦争のような世界は、相手に思いやりを持つという余裕がないような利己的意識が強く働く極限的な状況であるにもかかわらず、関係が継続的であると、自分の利益を守るためにも相手に対して協力的にならざるをえないような事態が発生するというのである。ちなみにアクセルロードの著書のタイトルは「協調の生成」(evolution of cooperation)で、evolution(進化)と名付けているのは意味深長です。
(根岸隆編:『経済学のパラダイム』より) |
|
第93夜 -英国の伝統
|
| 経済思想を考えるうえで、「ハテナ博士」はついついイギリスという国を中心に見る癖があります。といってもイギリスを訪ねたことはありませんが。イギリスという国、イギリス的な考え方、そしてその長く続いた伝統が好きなのです。ゲルマン的であるよりはアングロサクソン的なものの見方に同感を覚えます。何故なのでしょうか。自分でもよく説明ができませんが、一つの好きな理由を、例えば、カズオ・イシグロ*氏の『日の名残』という小説の中に見つけることができます。この本は伝統的なイギリス貴族に仕える執事の回想で語り継がれています。同名で映画にもなりました。アンソニー・ホプキンスの演ずる執事役がぴったりの渋い映画でしたが、あまりにも淡々としていて物足りない向きもあったかと思います。それはさておき、その小説のなかで主人のダーリントン卿が彼の雇った執事スティーブンスに次のように語り掛けるシーンがあります。
「何かが時代遅れになっても、この国では気づくのが遅すぎる。ほかの偉大な国々を見てみるといい。新しい時代の挑戦を受けて立つには、古い方法をーたとえ、どんなに愛されてきた方法でもだー投げ捨てねばならん。ほかの国はそれをよく知っている。だが、イギリスだけが違う・・・・・・」 *カズオ・イシグロ氏は日本生まれですが、5歳のときに家族と共に渡英、イギリスと日本の二つの文化を背景にして作家として英国最高のブッカー賞をこの『日の名残』で受けました。 そういえば舞台は英国ながらどこか日本的な叙情の流れる美しい小説です。 さて、イギリスの何が他の国と違うのでしょうか。伝統の力と言ってしまえばそれまでです。慣習を重んずる国民性、新しいものに直ちには飛びつかない落ち着き、ジェントルマンたる品格、そう、この本で執事の条件はと問われてスティーブンスは「品格です」と答えるシーンがありました。総じて「ハテナ博士」にこの英国の国民性を、「持続可能性」(sustainable)史観に求めることができると考えています。 |
|
第94夜 - 比較優位ということ
|
お互い経済学者は異論を唱えることで自らのアイデンティティを主張するのが常ですが、その中で珍しく共通した意見を持っているのが、「比較優位説」でありましょう。この理論のそもそもの提唱者はディヴィッド・リカードウで、その著『経済学および課税の原理』で述べられています。「比較優位」を説明するには通常、二国、二財を例にとっていろいろな例、例えばイギリスとポルトガル、亜麻と葡萄酒など、が使われています。もっと手近な例で説明いたしましょう。若田部氏より拝借しました次の表を見てください。
この表は、次のように読みます。それぞれの財(ネジ1本、ねぎ1本)を1単位生産するのにどれだけの労働者の数が必要かを示すものです。例えばネジ1本を作るには、日本では100人の労働者、中国では90人の労働者が必要であることを示しています。ねぎも同様に日本では120人、中国では80人の労働者が必要です。一見すると、中国はネジもねぎも両方とも安く生産でき、日本はどちらも高い、したがって日本はネジもねぎも両方とも高いのでどちらも中国から輸入したほうが有利のように見えますね。これを絶対優位と言います。ところがそうはならない、というのが比較優位の説なのです。日本で見ますとねぎよりもネジのほうが比較的に優位にあります。だから、日本はネジに、中国はねぎに特化することで両国にとって利益が生じる、というのです。そうすると日本は100人の労働者で作れるネジの生産物と交換に、120人分の労働の生産物であるねぎを手に入れることができます。 どうもピンと来ませんね。若田部氏は更に面白い例で説明しています。アインシュタインとタイピストの例。アインシュタインはひょっとしたらタイプを打つのも得意かもしれない。タイピストよりも早く打てるかもしれない。しかしアインシュタインは天才的な物理学者ですから、研究に全力を注ぐべきで論文はタイピストに任せるべきです。なぜなら、そのように分業することで全体としては一層成果が上がるからです。数多くの例題のなかで、この例は「ハテナ博士」が薦めるイチオシです。 (参考:若田部昌澄『経済学者たちの闘い』より) |
| 第95夜 -縦軸と横軸 |
最近の経済学は数学をふんだんに使って「ハテナ博士」のような文科系の出身者にはとんと判らぬことばかり。ところが高度な数学を駆使しながらごく基本的なことが無視されている?これが「ハテナ博士」のひがみというもの。有名な需要曲線と供給曲線のイロハを下に掲げてみましょう。
この図で右上がりの曲線(便宜上直線で描いています)は供給曲線、右下がりの曲線(便宜上直線)は需要曲線を表し、その交点で価格と数量が決まるという最も典型的な需給曲線です。例えば価格が下がると供給は減り(右上がり曲線)、需要は増える(右下がり曲線)とごく自然な現象を説明しています。けれどもちょっと待ってください。私たちが中学で習った関数y = f(x) は、xは独立変数で横軸に、yは従属変数で縦軸に夫々表すと教わりましたね。とすれば上の図の横軸には独立変数である価格が、縦軸には従属変数である数量が来なくてはならないのではないか、という疑問が湧いてきます。ところが経済学では縦軸に価格、横軸に数量をとり、価格の上下から説明していくのが慣行となっています。これはマーシャルから始まる描き癖なのです(マーシャルは数学に強い経済学者にもかかわらず)。以来この慣行は今日まで続いてきて、もう誰も不思議に思わないほど当たり前になっているのです。こんな些少なことにこだわるのはそれこそ「ハテナ博士」のいじわる癖なのでしょうか? |