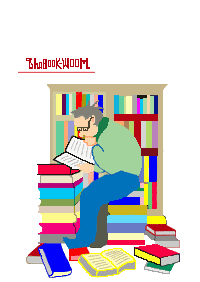前夜からの続き
|
第316夜から第320夜まで
|
|
第316夜 - ロスチャイルドの大博打
|
| ロスチャイルド家は、18世紀末にドイツのフランクフルトに誕生して以来今日まで世界最大の財閥として君臨しています。ロスチャイルドの伝説の一つとしてしばしば語られるのが、1815年のワーテルローの戦いで、イギリスウェリントン将軍がフランスナポレオンを破ったとき、ロスチャイルド(ネイサン・ロスチャイルド)は逸早くウェリントンの勝利をイギリスに伝えイギリス公債の暴騰を見越して莫大な収入を得たとされています。今日ではこの逸話を情報合戦の勝利として教訓めかして語られていますが(当時は伝書鳩を使って情報を伝えたとも言われる)、この最大の伝説が誤りであったとも伝えられています。ワーテルローの前後の英国の公債相場は何の変化も見せなかったからであります。その伝説の真偽はともかくとして、以後のロスチャイルド財閥の興隆は、5人兄弟の固い結束・金融・各地に展開された国際的活動・通信による屈指の機動力などを駆使して新境地を開拓して今日まで血筋をひきつつ受け継がれているのです。 |
|
第317夜 - ロイズ保険の誕生
|
|
第305夜で「コーヒーと経済学」と題してお話しましたが、その実例を一つお示ししましょう。広瀬隆氏によると、ロンドンのコーヒーハウスは、東インド貿易によって急激な発展をし、なかでもエドワード・ロイドが「ロイズ・コーヒーハウス」を開業して、貿易についてのニュースを伝える新聞の発行、ギャンブル、投機、郵便物の集配などあらゆるサービス業を行い、それが後に世界最大の「ロイズ保険」となったのでした。すなわち、1692年にロイドがロンバード街に店を移し、保険業を営んだからであります。たかがコービーハウスというなかれ、その世界的なロイズ財閥の発祥がここにあったのでした。
(参照: 広瀬隆『赤い盾』上 より) |
| 第318夜 -鉄の女 |
| サッチャーの意志や信念の強さを評して”鉄の女”と、彼女の首相在任中に呼ばれていました。鉄のように頑丈というイメージで付けられたと普通は理解されていますが、この呼び名の語源は少々違うようです。かのワーテルローの戦いでナポレオンを破ったウェリントンに付けられたニックネームで”鉄の公爵”(アイアン・デューク)との異名をとったのが始まりのようであります。何だ、意味は同じではないか、と思われるかもしれませんが、前夜の広瀬氏の著者によりますと、”冷徹さ”に加えて”残忍さ”が民衆の怒りを買って、わが身を守るために自宅に鋼鉄のシャッターを取りつけなければならなかったのに因んでイギリス人が風刺した、とのことなんだそうであります。あるいは19世紀のドイツで「ドイツ問題は鉄と血をもって解決されねばならぬ」と考えたビスマルクも”鉄血宰相”と呼ばれました。同じ鉄でも随分と違ったニュアンスを持っていますね。
(広瀬隆 同上書 上 p.179, 254) |
| 第319夜 - ファシズムとは |
| もともとファシズム(Fascism)という言葉は、イタリア語で「結束」を意味するfascioからきており、その語源は、古代ローマの執政官の権威の標(しるし)だった束かん(棒をたばねた間から斧(おの)の刃をみせたもの)から由来しています。それが現代に現れたのは、1919年にムッソリーニが組織した「戦闘ファッシ」(ファッシ・ディ・コンパティメント。ファッショはファッシの単数形)においてでありました。この組織がファシスト党に発展して政権を獲得し、ファシズム国家とかファシズム体制とか云われるようになりました。本来のローマに由来するファッショ(fascio)は横暴な支配者を倒す正義を意味したのでありますが、今日では”独裁”という意味に曲げられて用いられているようです。しかしいまさら支配者を倒す正義の味方といってはファシズム擁護のように聞こえますね。言葉の語源とその使われ方に違和感がかなりありますが、しかし言葉の意味の変遷はこのように間違って伝えられる、ということは自覚しておく要があろうかと思うのであります。
(出典: エンカルタ総合大百科2003より) |
|
第320夜 - 研究開発への姿勢
|
| 研究開発(R&D)のやり方は二つに分かれます。小さなものを積み上げて、そこで蓄積されたものを生かす、これが日本式の研究開発といえるでしょう。例えば今では英語として定着した”カイゼン”などが典型です。ところがアメリカやヨーロッパのR&Dは、経費と時間を掛けて大規模に行われます。また成功か失敗かの二つに一つの大勝負に賭けることもあります。だから、日本ではノーベル賞をとる機会がなく、一方彼らはノーベル賞は取るが市場のシェアを失うこともあるのです。
(参照: スティーブン・シュロスタイン 『エンド・オブ・アメリカ』上) |