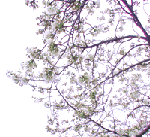|
第406夜から第410夜まで
|
|
第406夜 - CNNの姿
|
|
世界的なメディア企業であるCNNは、Cable News Network の略です。でも余りにも激しい超安上がりの取材方(一人でカメラマン、オーディオマン、編集者、レポーターまで兼ねる”ワン・マン・バンド”といわれる)をからかって、”CNNとは、CHICKEN NOODLE NEWS, つまり安っぽいチキン・ヌードルみたいなニュース”のことか?と揶揄されたりします。しかしCNN社長のショーンフェルトは一向に平気で、金を使う役目と節約する役目を同時に負わされ、ニュースの輪を回し続けていかねばなりませんでした。ここで少しばかり下ねたなエピソードを引用しますと次のようです(長くなりますので中略せざるをえませんが)。 全員が走り回ってニュースの輪を回し続けているので、ある女性ビデオ・ジャーナリストが男性の同僚に言ったものだ。「もちろんあなたと寝てもいいわよ。CNNの放送が終わったらね。」終わりのない放送ということの意味が皆によく分ってきた。キャスターはうっかりすると、 エピソードをもう一つ。 ホーム・ビデオ・マガジン誌の記者が、CNNのニュース報道の仕方には焦点が欠けているという批判を伝えたことがある。これに対する回答。 ちょっと待ってくれ。いいからちょっと待ってくれ。焦点って何だ。ずっと生でやっていてどうやって焦点なんか考えていられるんだ。焦点とは結果が分っているから出てくるもんじゃないのか?相手の正体が分らずに焦点を結べるか?新聞ならいいだろう。連中は一日中考えてから翌日の新聞を作ればいいんだから。雑誌なら一ヶ月ある。生のCNNに焦点がどうのこうの言う奴はアホだ! いやはや、かつての日本の猛烈社員、経営者もタジタジですね。 (参照:ハンク・ホイットモア『急成長のCNN』 下巻 p.9-11 なお原題はCNN:THE INSIDE STORYとありますから、余り公式の information ではなさそうです。) |
|
第407夜 - クライシス・ニュース・ネットワーク
|
|
ひとはまたCNNのことを”危機(クライシス)・ニュース・ネットワーク”ともジョークで言われます。CNNが情報を流しすぎるという議論が出たとき、それは思い上がりだといって次のように反論するのです。 それは最悪のエリート主義なのだ。そういう発想自体が、ある情報を与えられた視聴者がそれによって間違った行動を触発されるかもしれないという予断に基づいている。ある情報を”これは大衆に与えられるべきでない”と誰が決めるのか?どこで線を引けるというのか?・・・視聴者は充分タフな存在で、与えられたニュースをふるいに掛け、情報の中から重要なものをピックアップするだけの能力を十分持っている。ピックアップしたニュースをどう利用していくかは視聴者自身の問題だ。同じ間違いなら、情報を与えすぎる方を、与えなすぎるよりも私は選びたい。 (参照:同上書p.251-252) |
| 第408夜 - キツネに鶏小屋の見張りを頼む? |
|
少し古い書物ですが、バーナムという人の『コンピュータ国家』を読んだら、こんなことが書かれていました。要約しますと、アメリカ市民の伝統的な反応は、重大な問題が発生すると、それを取扱う新しい政府機関が設置されるというのだそうであります。ところがコンピュータの世界になると、言論の自由やプライバシーなど微妙な問題を含んでいますので、病気そのものよりも治療に投じた薬が命を奪う結果になりかねません。しかし情報そのものを検閲する政府の機関はアメリカ以外でもスウェーデン、フランスその他のヨーロッパに設置されてきました。そこで著者はこう指摘します。「アメリカでも同じようにキツネに鶏小屋の見張りを頼むという見通しは、現在の通信システムで進行している革命にとって最も皮肉な脅威になるかもしれない」と。
わが国でも情報流出、カード偽造、犯罪防止とプライバシーなどの問題が頻繁に生じている現状で、政府の規制とプライバシー保護とのからみ合いをどうするかが真剣に問われ、どこまで規制を掛けれるかが、喫緊事になっています。 (参照:デーヴィッド・バーナム『コンピュータ国家』 p.215,) |
| 第409夜 - ニートの存在 |
|
ニートとは、NEETで Not in Education, Employment, or Training の頭文字をとった用語です。この人たちが急速に増加していることが社会現象として捉えられ、将来どうなっていくのかが心配です。具体的には、いわゆる無業者で、「職に就いておらず、学校等の教育機関に所属せず、就労に向けた活動をしていない15 - 34歳の未婚の者」を言いいます。その数は凡そ52万人(2003年)と報じられています。しかも年々増加していく傾向にあるようです。これが労働市場のきびしさを反映した結果であるといっても、その影響は深刻であると考えます。ニートが失業者に数えられていないのも問題です。彼らが次第に歳をとっていきますと、一体就職、就業できるのかどうかが心配です。少子化対策が叫ばれる一方で職につかないニート族が増えていくという皮肉な社会現象は、格差社会あるいは大げさに言えば新自由主義の落とし子、すなわち、勝ち組と負け組に大きく分かれてしまう、そのなかでの象徴的な現象ではないでしょうか。
|
| 第410夜 - ポアンカレの逆説 |
| かりに、昨夜のうちに、宇宙にあるすべてのものが二倍の大きさになったとします。そんなに大きく変化したのならすぐに察知できるだろうと考えるでしょう。しかしすべての大きさが二倍になるのなら、物差しも巻尺もすべて二倍になるのですから、大きさの変化は知ることができません。これがジュール・アンリ・ポアンカレ(1854〜1912)が立てた史上最も有名な謎と言われています。例えば東京タワーを見ると、二倍になりますが、自分と東京タワーとの距離も二倍になっています。部屋の壁に掛けている写真は今や二倍になっていますが、自分の頭も二倍になり写真からの距離も二倍になっています。つまり誰がその大きさの変化を知り得ることができようか、という問題になります。では当のポアンカレはどういう結論を出したのでしょうか。ポアンカレは、本当は変化していないのだと言うのです。いなそういう変化は無意味だと言うのです。変化したというのは錯覚だと言うのです。昨夜すべてが二倍になったと言おうと、すべては元のままだと言おうと、同じ事態への記述のしかたが違うだけだと言うのです。このことは哲学上の問題としては実在論と非実在論に分かれる議論を呼び起こします。実在論は、人間の知識や観測とは別に外の世界があるのだと唱えます。一方非実在論に立つ人は、証拠を超越した真実はないと論じ、夜間に二倍になるのを誰も検出できないとすれば、二倍になったのはばかげている、と言います。昨夜すべてが二倍になったと言おうと、すべては元のままだと言おうと、同じ事態の記述のしかたが違うだけだと主張します。 ポアンカレの逆説はさらに物理学の分野でその証明をめぐってややこしい議論に化けていきますが、ここまで来ると「ハテナ」はついていけません。ただ何となく判ったようで判らない、”ブラックホール”やSFの世界ではありそうなことに思われるというのが精々のところです。 (参照: ウィリアム・パウンドストーン『パラドックス大全』より) |